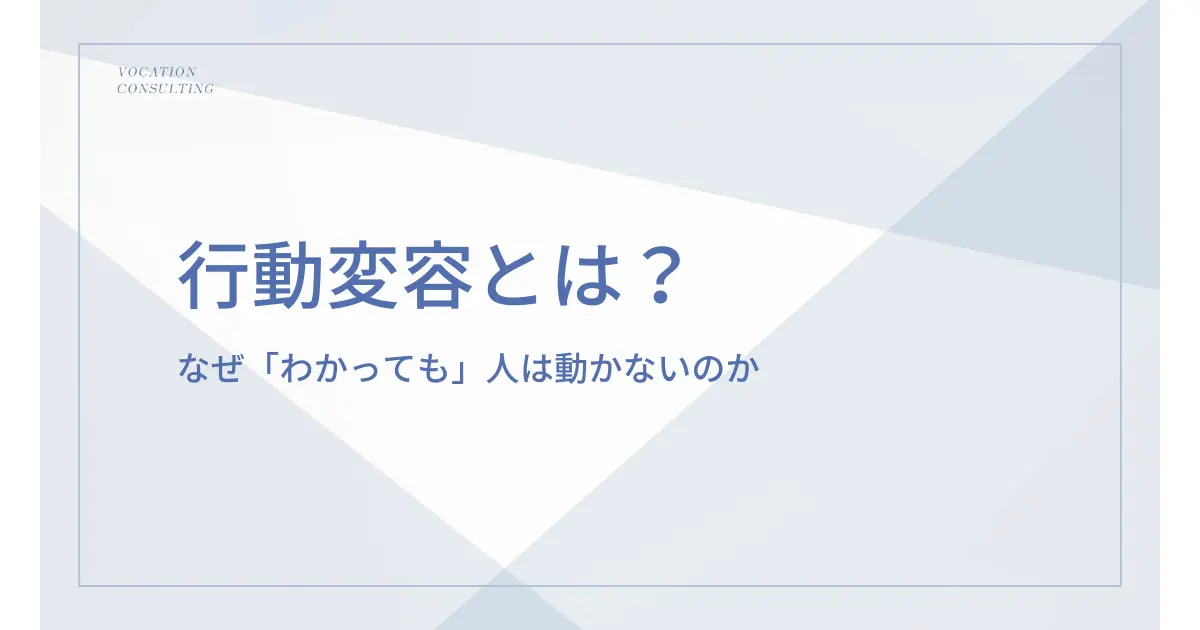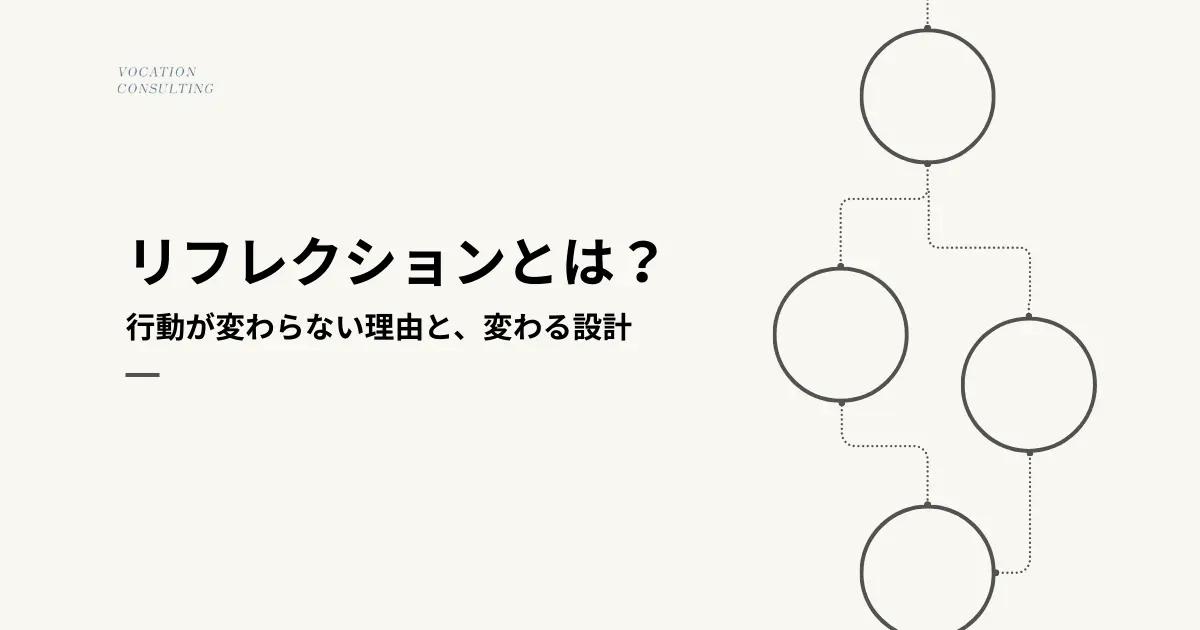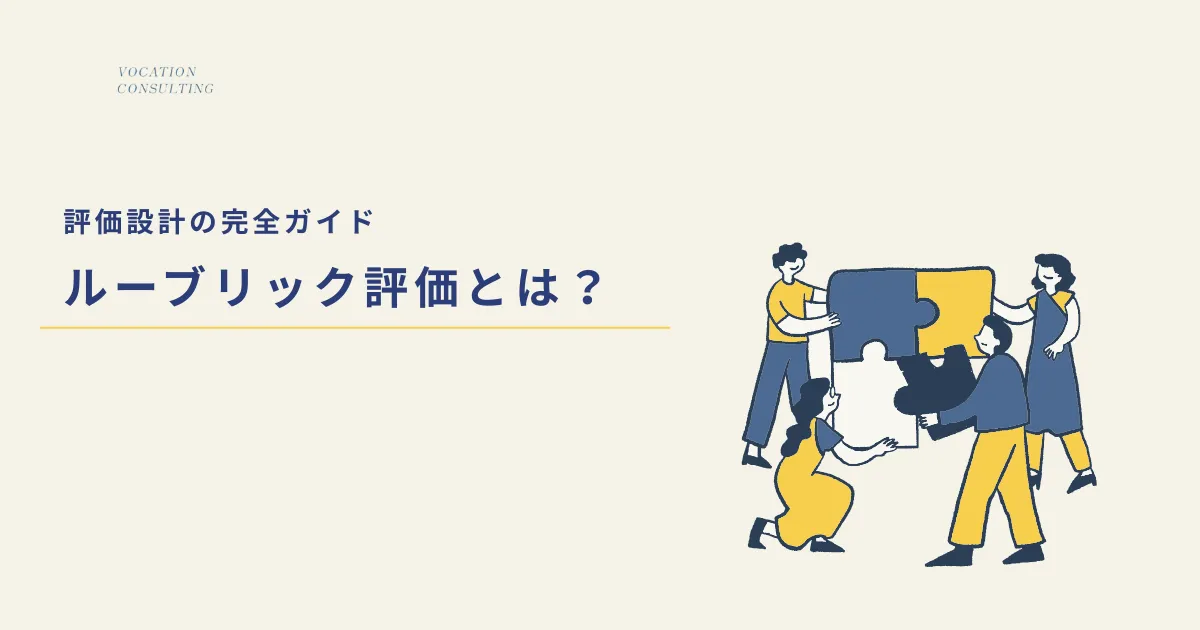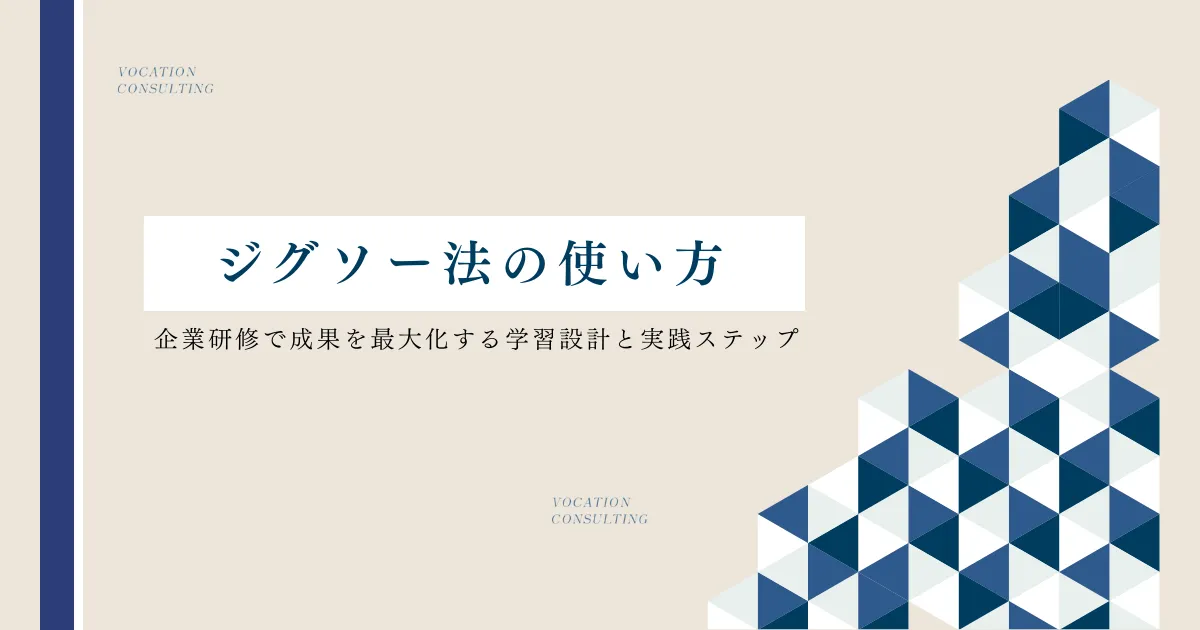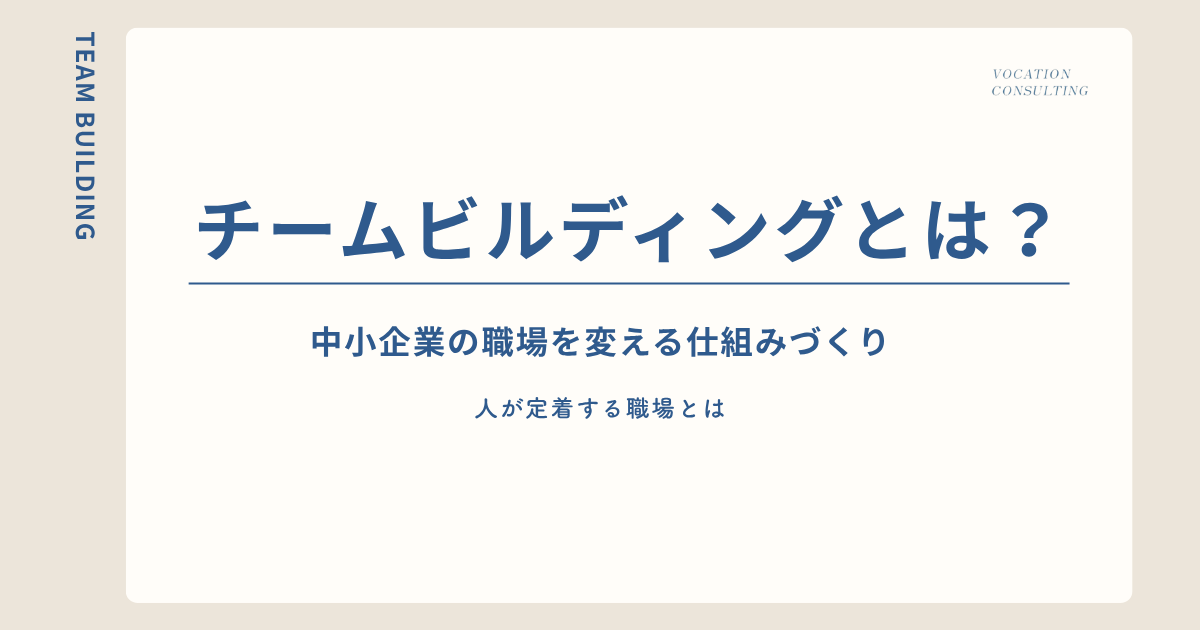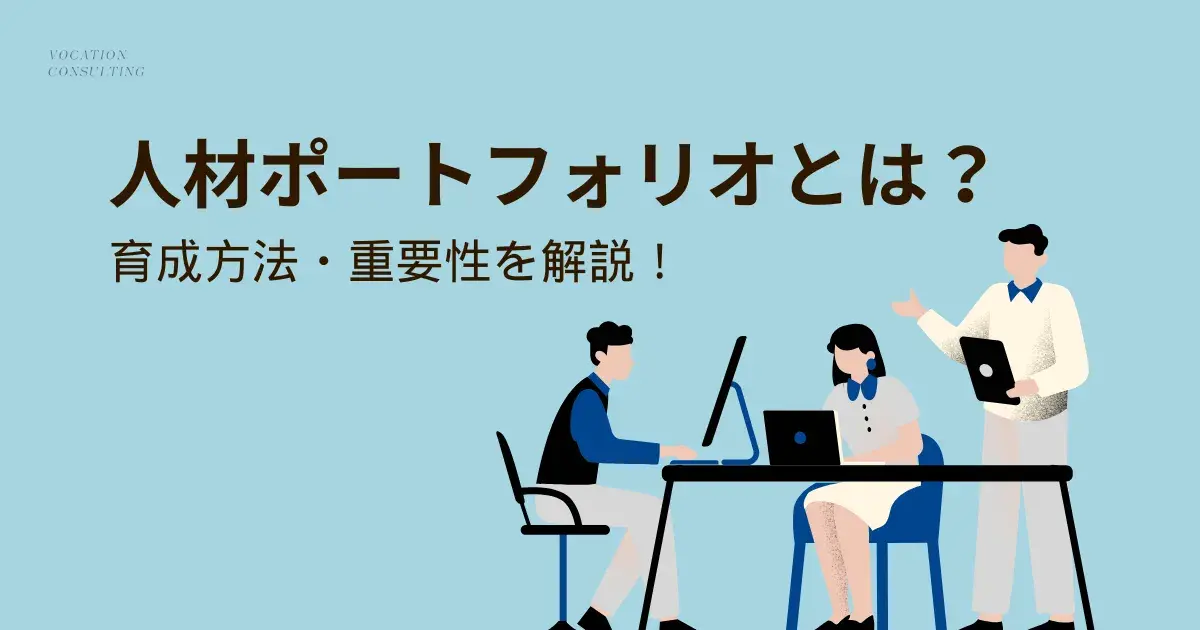「社内で研修を運用したい」
「外注費を削減したい」
「ナレッジを社内に残したい」
– そんな声から注目される“研修の内製化”。
しかし、いざ始めようとすると
「そもそも内製化ってどういうこと?」
「うまくいかない原因は何?」「何から手をつければいいの?」
と、手探りになる企業も少なくありません。
本記事では、内製化の基本から、よくある失敗・成功の仕組み・他社の具体事例までを網羅。読み終える頃には、「自社で取り組むべきこと」「支援を受けるべきこと」の判断ができるようになるはずです。内製化に少しでも関心がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
研修の内製化とは?外注との違いと注目される背景
「研修の内製化」とは、自社の人事部門や現場部門が中心となって、研修の設計・実施・運用を自社内で担うことを指します。具体的には、研修の目的設定や内容設計、教材づくり、講師の選定、実施後の振り返りまでを自社で行う運用スタイルです。
これに対し、従来のように外部講師や研修会社にすべてを任せる方法は「外注型」と呼ばれます。
外注との違い:一貫性・柔軟性・資産化の観点で大きな差
研修を外注する場合、確かにプロフェッショナルなコンテンツを短期間で提供できる一方で、自社の価値観や現場の実態にマッチしづらいという課題があります。内製化の場合、以下のような違いがあります。
| 観点 | 外注型 | 内製型 |
|---|---|---|
| 目的への一貫性 | 外部と連携が必要、ずれが生じることも | 経営方針・現場課題と直結しやすい |
| 柔軟性 | カリキュラム変更に制約があることも | 自社のペースで調整・改善が可能 |
| 教育資産化 | 外注先に依存/ノウハウが残らない | 教材・運営ノウハウが社内に蓄積され継続的に活用可能 |
なぜ今、研修内製化が注目されているのか?
近年、多くの企業が「内製化」に注目している理由には、以下の3つの背景があります。
1.DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
急速に変化する業務やツールに対応するには、現場の実情に合った研修が求められます。内製化により、変化に即応する教育体制が築けます。
2.人財不足と早期育成のニーズ
採用難の時代において、新人や若手の早期戦力化が必要不可欠です。内製化によって、現場の育成スピードに合わせた実践的な研修が可能になります。
3.ナレッジの属人化と引き継ぎ課題
ベテラン社員に偏ったOJTや暗黙知は、退職・異動で失われるリスクがあります。研修を内製化し、内容を形式知化・共有化することで、教育の属人化を防ぎ、再現性ある人財育成が実現します。
つまり、研修内製化は単なるコスト削減ではなく、戦略的な人財育成・組織力強化につながる手段として、多くの企業で検討・実践されているのです。
研修内製化の主なメリットとリスクとは?
研修を内製化することで、外注にはない多くの利点が得られる一方で、注意すべきリスクも存在します。ここでは、メリットとリスクを4つずつ対比形式で整理します。
内製化のメリット
1.自社ナレッジが活用・蓄積できる
社内に蓄積されたノウハウや事例を教材化でき、組織としての学習資産が残ります。
2.現場に最適化された研修ができる
現場で実際に求められているスキルや知識に即した、実践的な内容を設計できます。
3.柔軟に内容・頻度を調整できる
業務状況や育成フェーズに応じて、内容やスケジュールを自社判断で調整可能です。
4.外注コストが削減できる
講師費用やカスタム設計費など、都度の外注コストを抑えることができます。
内製化のリスク
1.設計・教材作成の負担がかかる
ゼロから作成する場合、資料設計や構成づくりに多大な時間と労力が必要です。
2.講師育成・仕組みづくりに失敗すると定着しない
教える側のスキルが未熟だったり、仕組み化ができないと、研修が継続しません。
3.属人化すると引き継ぎや改善が難しくなる
特定の担当者に依存すると、異動・退職時に内容が継承されず、改善も滞ります。
4.成果が曖昧になり、教育効果を可視化できなくなる可能性
評価指標やフィードバック設計が不十分だと、実施して終わりになりがちです。
内製化のメリットとリスクの対比図
以下の図は、研修内製化における主なメリットとリスクを対比的に整理したものです。
| 項目 | メリット | リスク |
|---|---|---|
| 教育資産化 | 自社ナレッジが活用・蓄積できる | 設計・教材作成の負担がかかる |
| 現場適応性 | 現場に最適化された研修ができる | 講師育成・仕組みづくりに失敗すると定着しない |
| 柔軟性 | 内容・頻度を自社の判断で柔軟に調整できる | 属人化すると、引き継ぎや改善が難しくなる |
| コスト面 | 外注に比べて継続的なコストを抑えやすい | 成果が曖昧になり、教育効果を可視化できなくなる可能性 |
研修の内製化は、コスト面や柔軟性、ナレッジ蓄積の観点では非常に有効ですが、導入や運用には設計力と仕組み化の視点が欠かせません。自社で完結させようとしすぎず、リスクが高い部分だけ外部の支援を活用するというバランスが成果を左右します。
研修を内製化する5ステップ|成功の仕組みを構築する方法
研修の内製化は、「ただ外注をやめて自社で研修を行う」だけでは成功しません。重要なのは、再現性のある仕組みとして設計・運用できるかどうかです。
ここでは、実際に多くの企業が導入して成果を上げている「研修内製化の5ステップ」をご紹介します。
ステップ① 教育の目的と対象を明確にする
まず最初に行うべきは、「何のために、誰に向けた研修を行うのか」を言語化することです。たとえば「管理職に対して理念浸透を図る」「新卒社員に業務スキルを定着させる」など、目的が明確でなければ、設計や評価がブレやすくなります。
ステップ② 研修構成とゴールを設計する
目的が決まったら、次に「何を、どの順番で、どのように学ばせるか」という構成と評価軸の設計を行います。
この段階では以下のような要素を整理します:
・研修テーマ(マネジメント/接遇/OJT など)
・回数と時間(例:1回90分×3回)
・到達ゴール(できるようになること)
・評価方法(アンケート/ワークの成果/上司のフィードバック)
ステップ③ 教材・ワーク・資料を整備する
研修の質を左右するのが「教材」です。ここでは、スライド・ワークシート・講師台本などを標準化し、誰でも再現できる状態に整えることが求められます。
・スライド資料:構造化されたレジュメ
・ワークシート:実務に近い演習問題
・講師用台本:話す順序や問いかけの例
できれば、既存の資料を活用しつつ、フォーマット化しておくと属人化を防げます。
ステップ④ 講師の育成と関係者の役割分担を明確にする
内製化の肝は「講師の質と体制」にあります。現場社員が講師になる場合は、ティーチングスキルやファシリテーションの育成支援が必要です。
同時に、人事・現場・経営層の役割を以下のように分担しておくとスムーズです:
| 役割 | 担当内容 |
|---|---|
| 人事部門 | 設計支援・教材作成・評価システムの整備 |
| 現場部門 | 講師の担当・フィードバック・事後指導 |
| 経営・マネジメント | 目的の明示・実施への協力・評価結果の活用 |
ステップ⑤ 効果測定と運用の仕組み化
最後に重要なのが、「やりっぱなしにしない仕組み」を整えることです。効果測定のフレームとしては、KPT(Keep/Problem/Try)や振り返りシートが効果的です。
さらに以下を取り入れると、継続改善につながります:
・研修後アンケートの定型化
・現場レビュー会(月1回など)の定例化
・研修実施記録・改善記録の管理
この5ステップを踏むことで、属人的な場当たり的な研修から脱却し、「継続的に成果を出す研修の仕組み」へと変えていくことができます。内製化の成功には、プロセスの設計と社内連携の構築が不可欠なのです。
研修内製化でありがちな失敗とその対策
研修を内製化する際、「最初はうまくいっているように見えるが、だんだん形骸化してしまう」「現場任せにして制度として続かない」といった悩みをよく耳にします。
これは内製化に取り組む企業に共通する“あるあるの失敗”ですが、いずれも事前に対策できる内容ばかりです。以下に、よくある3つの失敗パターンとその解決策を整理します。
失敗1:講師任せにして教材が属人化する
現場の経験豊富な社員が講師を務める場合、その人の知識や話し方に頼りすぎて、教材や進行がブラックボックス化することがあります。その結果、「あの人じゃないとできない研修」になってしまい、引き継ぎも改善も困難に。
▶ 対策:フォーマットと台本で“再現可能”な教材にする
・スライドやワークシートに構成テンプレートを設ける
・講師が話す内容を台本化し、誰でも実施できる形にする
・資料の保管・共有ルールを決めて、ナレッジとして蓄積する
失敗2:現場任せで制度化されない
「とりあえず現場に任せよう」と始めた研修が、継続性や統一性のない“場当たり的な施策”に終わることもよくあります。実施の頻度や評価方法がバラバラで、振り返りや改善もされないケースです。
▶ 対策:評価指標と運用ルールを明文化する
・「この研修で何ができるようになれば合格か」をあらかじめ定義する
・実施回数・実施単位・報告ルールなどを仕組み化する
・評価のためのアンケートやレビューシートもテンプレート化
失敗3:「最初だけ盛り上がる」…継続されない
研修を始めた当初は盛り上がっていても、半年後には実施されなくなる、改善されないという問題も起こりがちです。
これは、「振り返り」「効果測定」「改善提案」といった仕組みが用意されていないことが原因です。
▶ 対策:改善サイクルと定例レビューで運用を“文化化”する
・KPTやアンケート結果をもとに改善点を毎回記録する
・月1回など、定期的なレビュー会議を設けて改善を共有
・「やること」ではなく「続けて成果を出すこと」を目標に置く
内製化成功のカギは「仕組み化+テンプレ活用+一部外部リソースの併用」
すべてを自社で完結させようとすると、時間も人財も足りずに形骸化してしまうことがあります。
重要なのは、以下の3点をバランスよく取り入れることです:
・教材や運用ルールのテンプレート化による属人化防止
・評価・改善を仕組みとして定着させる仕掛けづくり
・必要な部分は外部リソース(教材作成・講師育成など)を柔軟に活用
内製化の目的は「自社に合った継続可能な教育体制をつくること」。 部分的に支援を取り入れながら、仕組みと文化にする視点で進めることが、長期的な成功につながります。
業種・テーマ別|研修内製化の成功事例
「研修の内製化」は、業界や企業規模を問わず、さまざまな組織で導入が進んでいます。
ここでは、ヴォケイション・コンサルティングの支援を通じて、社内教育の仕組み化と成果創出に成功した3社の事例をご紹介します。
製造業(従業員300名)|外部依存を脱却し、社内講師体制を構築
外部講師による研修に依存していた同社では、コスト負担と教育の一貫性に課題がありました。 そこで「プロ社内講師養成トレーニング」を導入し、社内講師による内製研修の運用体制を構築。
教材作成支援・登壇練習・設計ノウハウを通じて、教育の質とコスト削減の両立を実現しました。
製造業(従業員100名)|自信を持てる研修運営へ、課題を一つずつ解消
研修担当者が孤立し、手探りで研修を設計・実施していた企業では、実施自体が目的化しがちでした。「社内研修課題解決サポート」の導入により、個別課題の見える化と改善支援を実施。
テンプレ・チャット支援・講師トレーニングを通じて、効果的な社内研修を自走できる体制が整いました。
サービス業(従業員200名)|全社共通の研修体系で教育格差を解消
事業部ごとに育成方針や教材がバラバラだった企業では、教育品質のばらつきが大きな課題でした。「プロ社内講師養成トレーニング」を活用し、事業部を超えた共通教材・共通言語の定着を支援。
その結果、教育格差を是正し、部門間の連携・実務パフォーマンス向上にも寄与しました。
これらの事例に共通するのは、現場が自ら「教える力」と「仕組み」を持ったことです。
研修の内製化は、単なるコスト削減だけでなく、組織全体の人財育成力を底上げする取り組みです。
すべて内製化すべきではない|最適なバランスとは?
「研修をすべて自社で行うべきか?」というと、必ずしもそうではありません。重要なのは、自社で担うべき領域と、外部のプロフェッショナルを活用すべき領域を明確に線引きすることです。
自社で担うべきこと
・経営や人事戦略と連動した育成方針の設計
・自社特有の業務や価値観を反映したナレッジの可視化
・現場の実情を踏まえた実施運営・現場浸透
こうした部分は、社内でしか把握できない情報や文化に基づくため、内製化の価値が高まるポイントです。
外部を活用すべきこと
・論点整理・設計視点を要する教材作成や体系化
・客観性や指導スキルが求められる講師育成トレーニング
・PDCAを機能させるための評価指標や効果測定の仕組みづくり
これらは専門的な知見・工数が必要なため、信頼できる外部パートナーの力を借りることで、効率と効果が両立できます。
「全部自社でやる」よりも、「自社の強みは自社で活かし、プロに頼る部分は頼る」ことで、より持続可能で成果の出る内製化が可能になります。
まず何から始めればいい?準備チェックリスト
「研修を内製化したいが、何から始めていいかわからない…」
そんな担当者の方ために、内製化を進める前に確認すべき準備のポイントをチェックリストとしてまとめました。
教育の目的と対象者は明確か
まず、[いつまでに、誰を、どんな状態にしたいのか?」を明確化する。次に、その実現のために「いつ、誰に、何を、どの程度、なぜ学ばせたいのか?」という目的を明確化する。まずはじめにこれら目的の明確化が欠かせません。ここが曖昧なまま進めると、研修内容がブレやすくなります。
現場と人事で役割分担できているか
内製化は「現場まかせ」「人事まかせ」ではうまくいきません。両者の役割分担を事前に整理し、連携体制を築くことが重要です。
教材や評価設計のテンプレートがあるか
ゼロから作るのではなく、共通のフォーマットがあると準備の負担が減り、複数の担当者でも一定の品質を保てます。
実施後の改善サイクルは設計されているか
「やりっぱなし」で終わらせないために、レビューや改善の仕組みを設けておくことが成功のカギになります。
これらの項目をチェックすることで、研修内製化の「つまずき」を防ぐことができます。
もし整理に迷う場合は、まずは現状の課題を一緒に整理してみませんか?
まとめ|内製化は“仕組み”で決まる
研修の内製化は、単に外注コストを減らす手段ではありません。*「自社らしい育成の仕組みをつくること」が最大の目的です。
うまくいく企業には共通して、「目的の明確化」「教材の仕組み化」「講師体制の構築」「改善サイクルの定着」といった仕組みがあります。一方で、属人化・形骸化・負荷集中といった課題に陥る企業も少なくありません。
だからこそ、最初の一歩は “全部自社でやろうとしすぎないこと”。社内で担うべきこと・外部に頼るべきことを整理し、再現可能な内製化を目指すことが重要です。まずは、自社の現状と課題から整理してみましょう
▶ 課題整理の無料相談はこちら