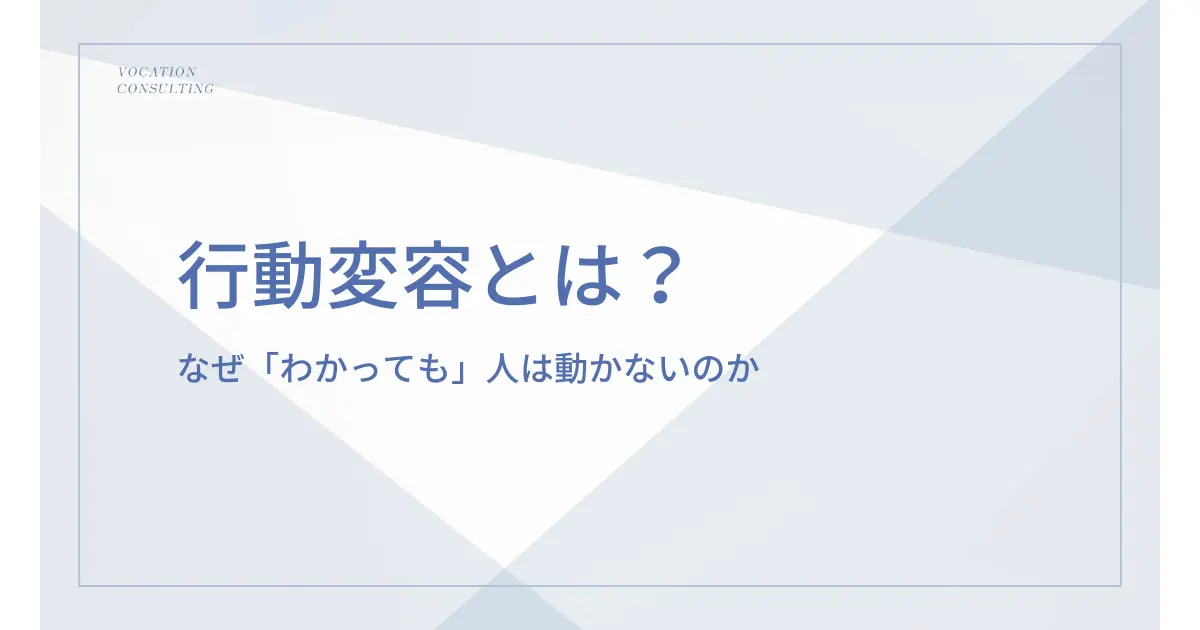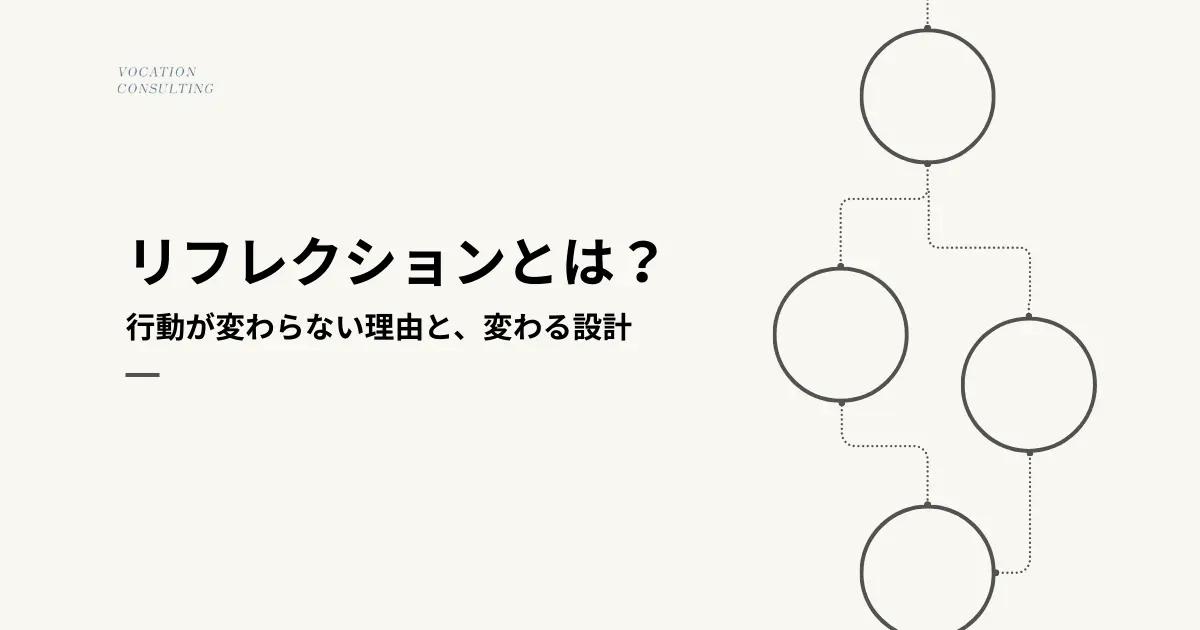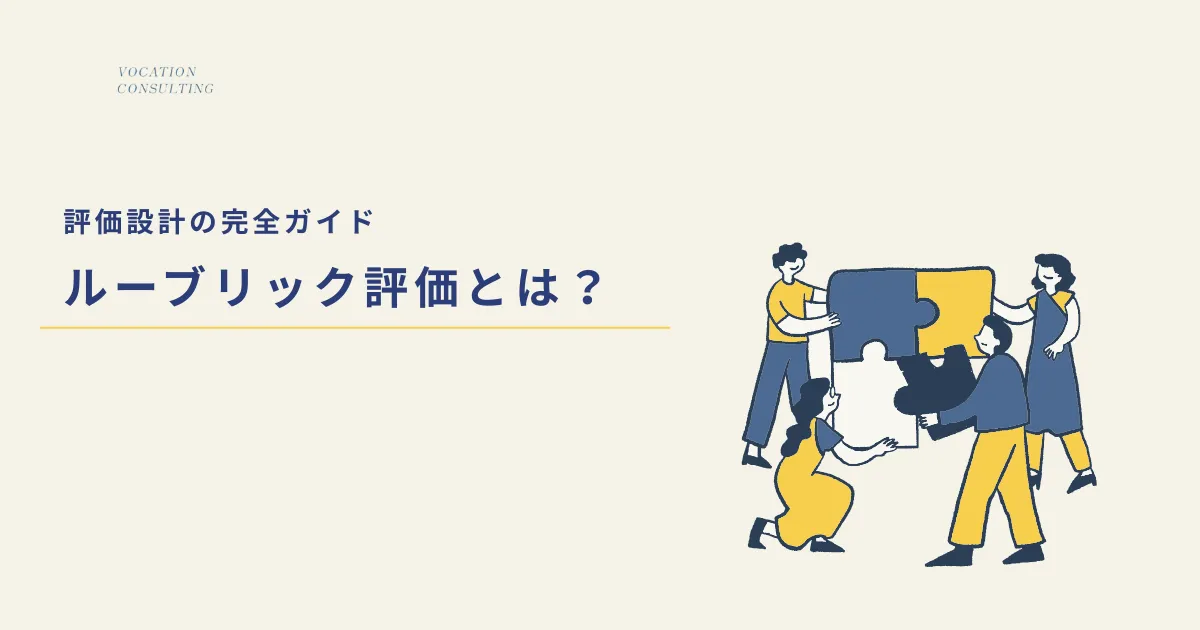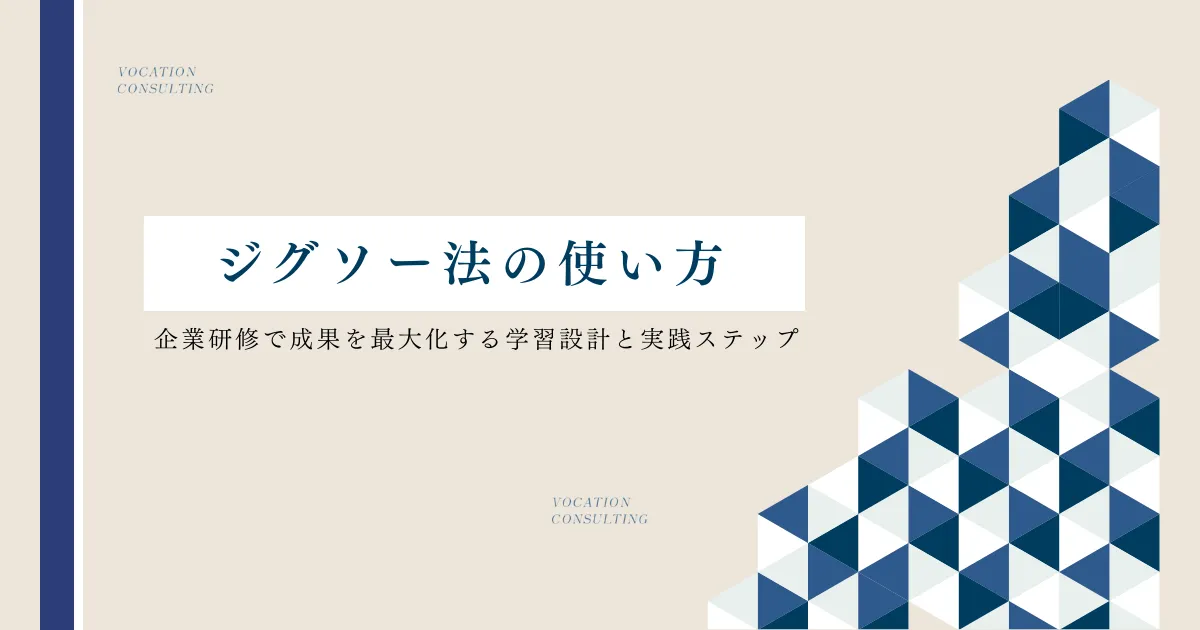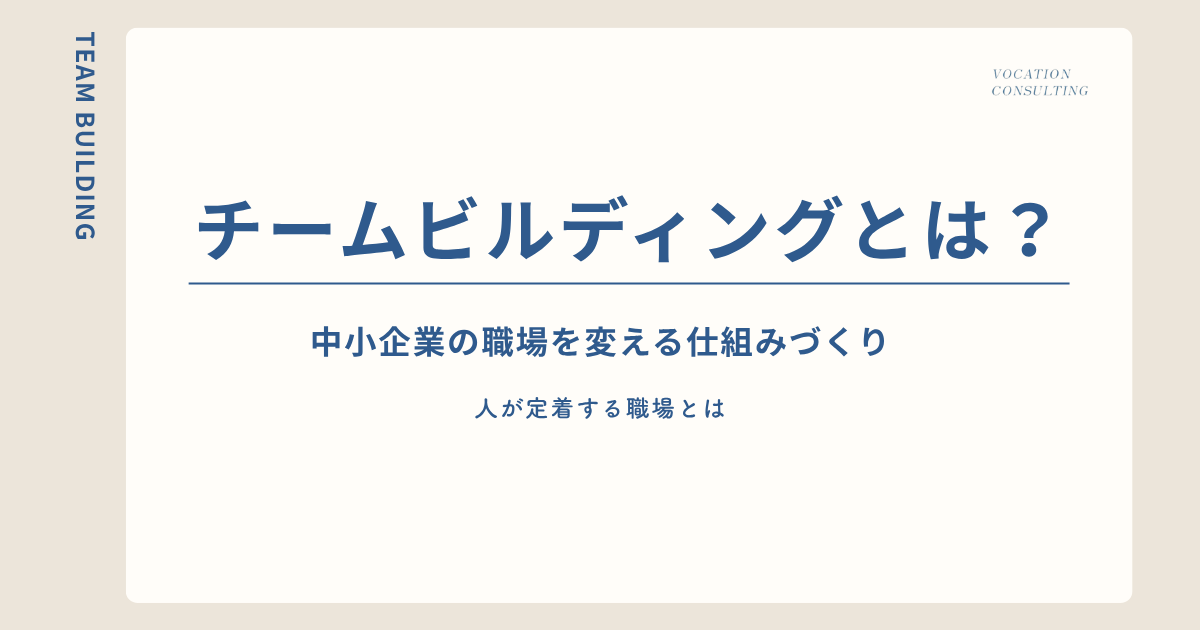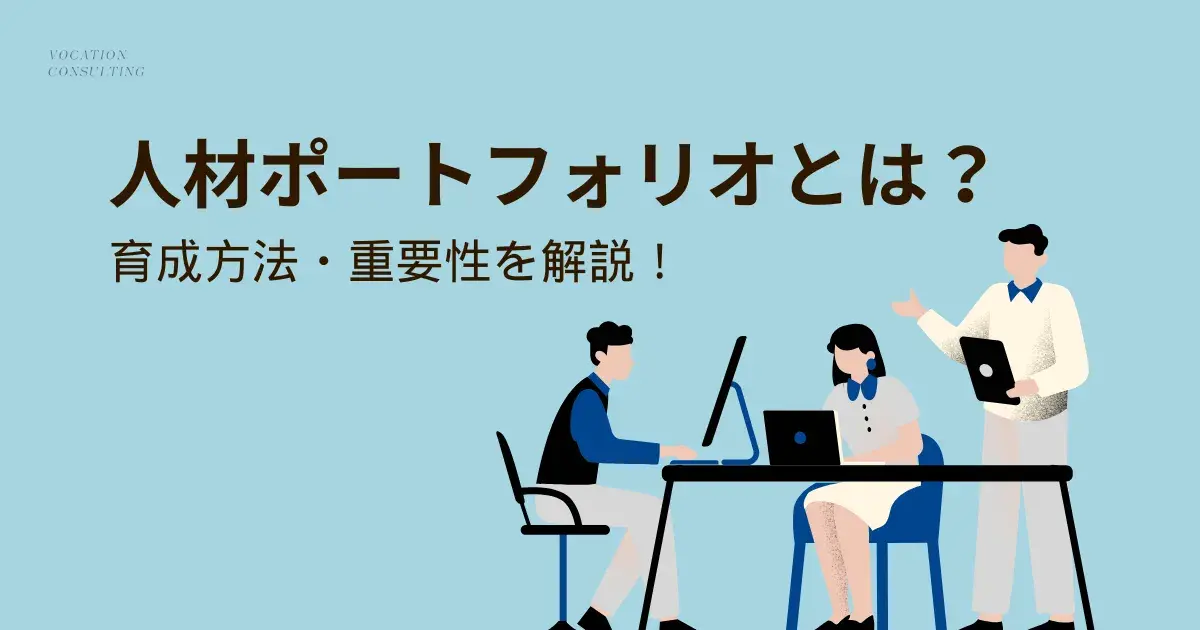「研修を実施しても、現場での変化が感じられない」「そもそも資料の作り方がわからず手が止まっている」-そんな悩みを抱える人事・研修担当者、現場マネージャーの方も多いのではないでしょうか。
実は、研修の成果は“資料の構成と見せ方”で大きく変わります。受講者に伝わり、行動につながる資料には、押さえるべき「型」と「工夫」があります。
本記事では、伝わる研修資料の作り方を5ステップでわかりやすく解説。社内研修の質を高めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
研修資料の作成目的とは?よくある失敗と成功の分かれ道
そもそも研修資料とは何か?目的と役割を明確にしよう
研修資料とは、受講者に伝えたい内容を整理し、理解と行動を促すための「伝達ツール」です。単なるスライドや配布物ではなく、研修全体の目的(知識習得・意識改革・行動定着など)を達成するための“設計されたコミュニケーション”の手段といえます。
そのため、研修資料を作る際には「何をゴールにするのか」「受講者にどう行動してほしいのか」を明確にした上で、それに合わせて構成・内容・表現方法を考えることが重要です。
ありがちな失敗パターン
研修資料の作成でよくある失敗には、以下のようなパターンがあります。
・情報の詰め込みすぎ:すべてを伝えようとして、かえって焦点がぼやけてしまう
・構成がバラバラ:話の流れが整理されておらず、受講者が理解しづらい
・文字ばかりで読まれない:視覚的な工夫がなく、スライドを見ただけで疲れてしまう
これらは「目的」と「受講者視点」を見失ってしまった結果、起こりがちな落とし穴です。
成果が出る研修資料に共通する3つの特徴
成果につながる研修資料には、以下の3つの共通点があります。
1.目的が明確
資料の冒頭で「何のための研修か」「どんな状態になれば成功か」が明示されているため、受講者の意識がぶれません。
2.構造的に整理されている
導入→本題→まとめ→アクションという流れが自然で、話の筋道が追いやすく、理解が深まります。
3.視覚的にわかりやすい
図表・アイコン・余白などを活用し、直感的に内容が伝わる工夫が施されています。資料を読むだけでもポイントが把握できるのが特徴です。
こうした要素を押さえた資料こそが、受講者の理解と実践を促し、「やって終わり」にならない研修を実現します。
研修資料の作り方|成果につながる5ステップと実践ポイント
成果の出る研修資料は、行き当たりばったりでは作れません。大切なのは、「誰に・何を・どう伝えるか」を段階的に設計すること。ここでは、伝わり、実践される資料を作るための5ステップをご紹介します。
① 目的とゴールを設定する(ビジネス成果・受講者行動)
まずは「この研修で何を達成したいのか?」という目的を明確にします。たとえば、「新入社員の基本マナーを習得させる」「管理職に部下育成の考え方を定着させる」といった、ビジネス成果に直結する行動ゴールを設定しましょう。
目的が曖昧なまま資料を作ると、伝える内容もブレてしまいます。逆に、ゴールがはっきりしていれば、「何を入れて、何を削るか」の判断がしやすくなります。
② 受講者のペルソナを明確にする(誰に何を伝えるか)
次に、「受講者はどんな人か?」を具体的に想定します。新卒社員、中堅社員、管理職、営業職など、対象によって必要な情報や伝え方は大きく異なります。
受講者の知識レベル・業務内容・現場の悩みなどを踏まえた上で、「どんな言葉で、どこまで説明すべきか」を設計すると、伝わる精度が格段に上がります。
③ 構成を設計する(導入・本編・まとめ・実践促し)
いきなりスライドを作るのではなく、まずは「構成設計」から始めましょう。基本は次のような流れです。
・導入:研修の目的・ゴール・受講者のメリットを提示
・本編:知識やスキルの解説、事例、注意点など
・まとめ:重要ポイントの振り返り
・実践促し:明日からどう活かすかを明文化(ワークや問いかけ)
この構成を意識することで、情報が整理され、理解・記憶・実践の流れが自然に生まれます。
④ スライド・ビジュアル化する(図解・視覚重視)
構成ができたら、スライドに落とし込んでいきます。ここで意識すべきは「視覚で伝える」という視点です。
・長文よりも箇条書き
・表や図解を活用
・キーワードを目立たせる
・1スライド1メッセージを原則に
視覚的に整理されたスライドは、受講者の集中力を高め、理解と記憶にもつながります。
⑤ 推敲・フィードバック・テスト運用(改善ループ)
資料が完成したら終わりではありません。伝わるかどうかは「受講者視点での検証」が重要です。
・同僚や先輩に見てもらい、わかりにくい点を確認
・テスト研修で受講者の反応を観察
・フィードバックをもとに修正 → 本番へ
この改善ループを回すことで、研修効果の高い資料へと洗練されていきます。
伝わる資料に欠かせない構成・デザインのコツ
効果的な研修資料を作るには、内容だけでなく「見せ方」にも工夫が必要です。どれほど優れた情報でも、構成やデザインが伝わりにくければ、受講者の理解や記憶にはつながりません。ここでは、誰でも実践できる3つのポイントをご紹介します。
1スライド1メッセージの原則
伝えたいことを詰め込みすぎて、1枚のスライドに複数の要素を並べていませんか? 「1スライドにつき1つのメッセージ」を徹底することで、受講者の理解負荷をぐっと軽減できます。
たとえば、「報連相の重要性」というテーマなら、「報告の意義」「連絡の手順」「相談のタイミング」をそれぞれ1枚ずつに分けて説明するのが理想です。一目で何を伝えたいかが分かる構成が、理解と記憶の定着につながります。
視覚で理解できる図・表・アイコン活用
スライドにおける視覚要素の活用は、理解を助ける大きな武器です。特に、以下のような視覚表現が効果的です。
・フロー図:業務プロセスや変化の流れを説明する際に有効
・マトリクス図:分類や比較、優先順位の提示に便利
・アイコンやピクトグラム:複雑な概念も直感的に伝わる
文字だけの資料と比べ、視覚情報が加わることで印象に残りやすくなり、研修後の行動変化にもつながります。
研修スライドにおすすめの無料テンプレート紹介(PowerPoint/Canvaなど)
「デザインに自信がない」「1から作るのが大変」という方には、テンプレートの活用がおすすめです。研修資料に適した無料テンプレートが多数公開されており、構成や配色もプロ仕様で整っているため、時短にもなります。
▶おすすめツール例:
・PowerPoint:Microsoft公式テンプレートやSlideModelの無料素材
・Canva:直感的な操作で編集可能。プレゼン用テンプレが豊富
・Google スライド:クラウド共有しやすく、共同編集にも便利
テンプレートを上手に活用すれば、構成や視認性が整った資料を短時間で作成でき、内容に集中する余裕が生まれます。
資料の構成やデザインは、単なる“見た目の工夫”ではなく、研修の成果を左右する重要な要素です。伝わる資料づくりの一歩として、まずはこうした基本ポイントを押さえてみましょう。必要であれば、テンプレート付きの資料もあわせて活用してください。
内製化で研修効果を高めるポイントと体制作り
ここまで、伝わる研修資料の作り方や構成・デザインの工夫を見てきましたが、実際に社内で研修を継続的に運用していくには、「仕組み」と「体制」づくりが欠かせません。とくに近年は、外注から内製へと舵を切る企業も増えており、その背景には“現場に即した研修”へのニーズの高まりがあります。
社内で回せる「仕組み」と「ナレッジ化」がカギ
研修を一度きりで終わらせず、継続的に改善・展開していくには、担当者個人に依存しない再現可能な「仕組み」と、学びを社内に蓄積する「ナレッジ化」が重要です。
たとえば以下のような仕組みを整えることで、属人化を防ぎ、誰でも一定の品質で研修を実施できるようになります。
・テンプレート化された資料・進行マニュアルの整備
・研修のゴール設定・進行台本・フィードバックシートの共有
・実施記録や受講者アンケートをもとにした改善ループの構築
さらに、実施した研修内容・反応・成果などをナレッジとして残しておくことで、次の企画や担当者交代時にもスムーズな引き継ぎが可能になります。研修が「一過性のイベント」で終わらず、「継続的に価値を生み出す仕組み」として社内に定着します。
外部講師との併用も有効。内製化と外注の使い分け方
内製化はすべてを自社で完結することが目的ではありません。テーマや目的によっては、外部の力を借りることも大切な選択肢です。
たとえば以下のような使い分けが効果的です。
・外注が向いているケース
法律・ハラスメント・DXなど、専門性が高く最新知識が求められる分野
社外視点での刺激を与えたい場合や、会社全体にインパクトを与えたい場面
・内製が向いているケース
自社の業務に密着した実践的な内容(例:接客研修・社内ルール・OJT教育)
現場の実情を踏まえた柔軟な設計・運営が求められる場合
このように「社内で育てる研修」と「社外のプロに任せる研修」をうまく使い分けることで、コストを抑えながら研修効果を最大化することが可能です。
社内で研修を効果的に運用していくには、単に資料を作るだけでなく、それを活かす体制としくみが必要です。内製化を通じて、研修が“教える場”から“行動を変える場”へと進化することを目指しましょう。
研修資料の作り方に関するよくある質問(FAQ)
研修資料づくりに取り組む中で、多くの担当者が抱える疑問をまとめました。初めて資料を作る方はもちろん、すでに実施している方にも役立つ内容です。
Q1:資料はパワポ以外でも作れますか?
はい、PowerPoint以外でも資料作成は可能です。最近では以下のようなツールも多く活用されています。
・Canva:テンプレートが豊富でデザインが苦手な方にもおすすめ。ドラッグ&ドロップで簡単に資料が作れます。
・Googleスライド:ブラウザで共同編集ができるため、複数人での作業に便利です。
・PDF資料:KeynoteやWordなどで作成後にPDF化することで、配布・印刷しやすくなります。
社内のIT環境や配布方法に合わせて、最適なツールを選びましょう。
Q2:文字が多くなりがちなのですが、どうすればいい?
まず意識したいのは「スライドは説明書ではなく、話すための補助ツール」という点です。以下のような工夫で、スライドの情報量を適切に抑えられます。
・箇条書きにする(1スライド3行以内が目安)
・図・イラスト・アイコンを使って視覚で伝える
・話す内容はスピーカーノートに書き、スライドには要点のみ
「読む資料」ではなく「聞いて理解する資料」を意識して設計すると、伝わりやすくなります。
Q3:受講者の反応を上げるにはどうすればいいですか?
受講者の反応を高めるには、単に情報を伝えるだけでなく、“参加型”の設計にすることがポイントです。
・ワークシートやチェックリストを使って「自分ごと化」する
・実例や失敗談など、リアリティのある内容を入れる
・小グループでのディスカッションや質問タイムを設ける
また、資料冒頭で「この研修で何が得られるか(メリット)」を明示することで、受講者の集中力や積極性が大きく変わります。
Q4:他社はどうやって資料を共有・運用していますか?
多くの企業では、以下のような方法で研修資料を共有・再利用しています。
・社内ポータルやGoogleドライブでフォルダ管理
・テンプレートや進行台本をナレッジとして残す
・受講者のフィードバックを踏まえて毎回アップデート
また、一部の企業ではLMS(学習管理システム)を活用して、資料の配布・受講状況の可視化・効果測定まで一元管理しているケースもあります。
重要なのは「資料を作って終わり」ではなく、「改善・再活用できる仕組み」を持つことです。
このようなよくある悩みや運用の工夫を知っておくことで、研修資料のクオリティも、運用の効率も大きく向上します。はじめは小さくても、着実に改善していくことが成功のカギです。
まとめ|伝わる研修資料づくりは「仕組み化」と「継続改善」がカギ
研修の成果は、資料のクオリティ次第で大きく変わります。ただ知識を伝えるだけでなく、「どう伝えれば行動につながるか」を考え抜くことで、研修は“受けて終わり”ではなく“現場を動かす”力になります。
本記事でご紹介した5ステップやテンプレート活用の工夫をもとに、まずは身近な研修から改善を始めてみてください。
また、社内で研修を継続的に実施していくには、資料だけでなく運用体制そのものの「内製化」も重要なテーマです。以下の記事では、社内研修を効果的に回すための体制作りについて詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
さらに、研修資料の企画・構成・デザインまでをまるごとプロに任せたい方には、当社の【研修コンテンツ企画制作代行サービス】もご活用いただけます。
▶ 研修コンテンツ制作代行サービス|現場で使える研修資料をプロが制作
現場に根づく、効果的な研修の実現に向けて、ぜひご相談ください。