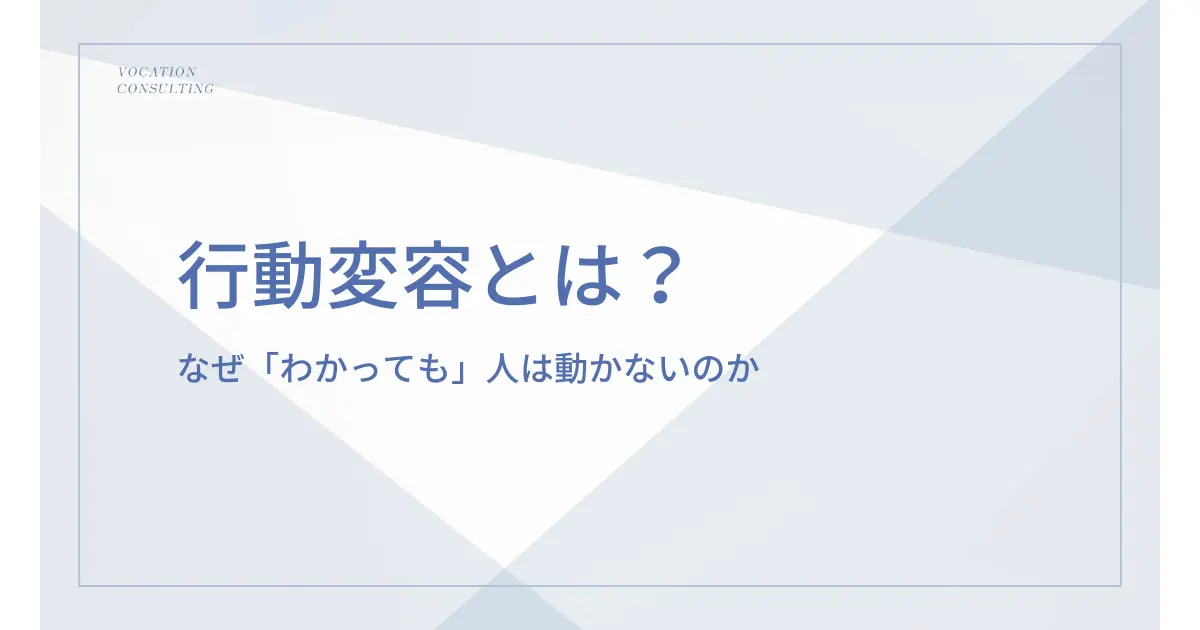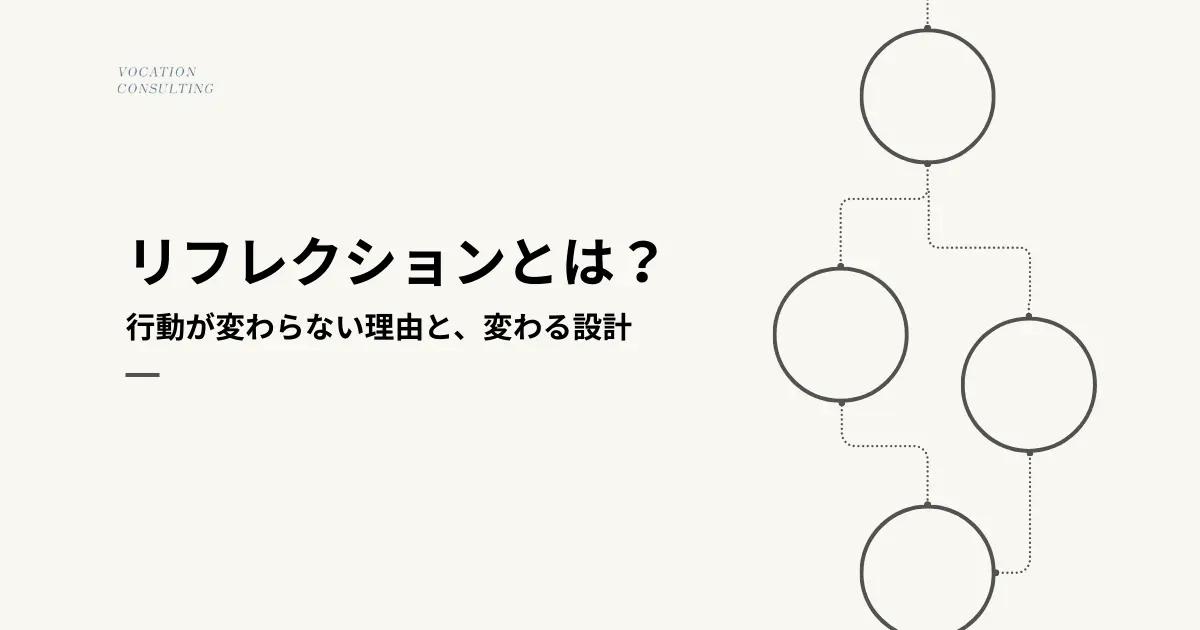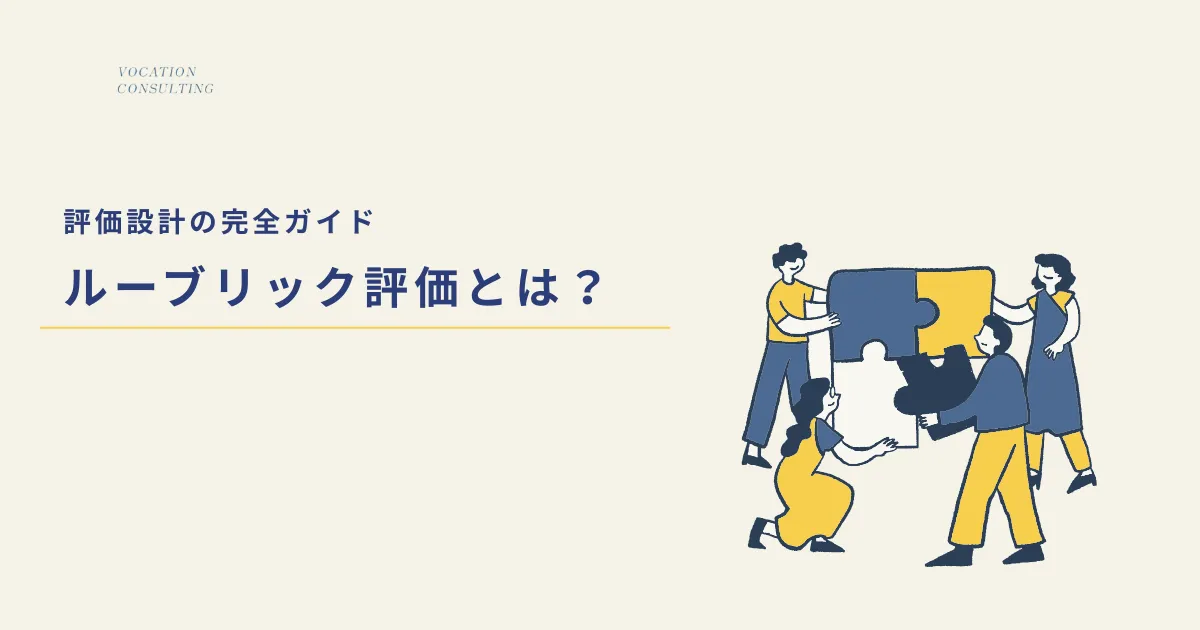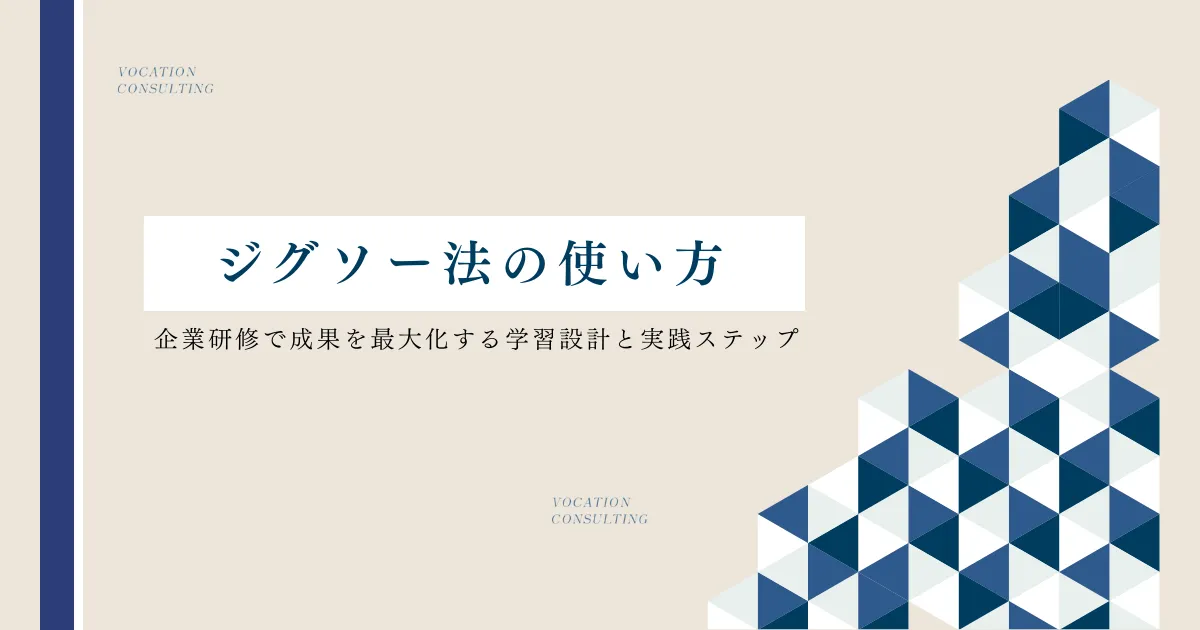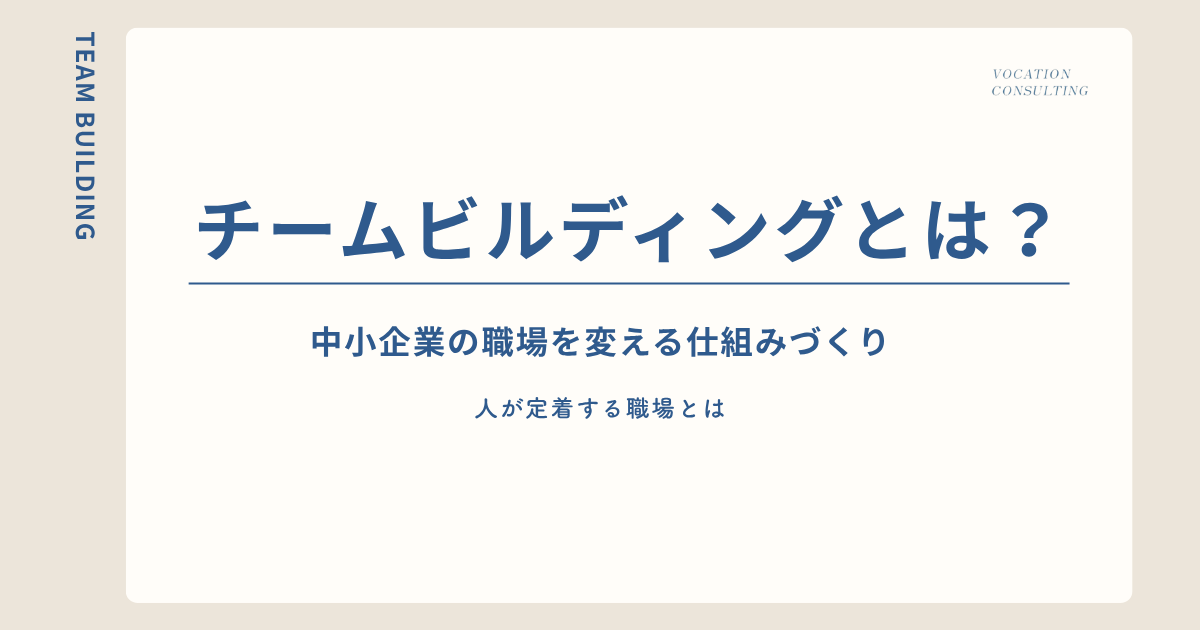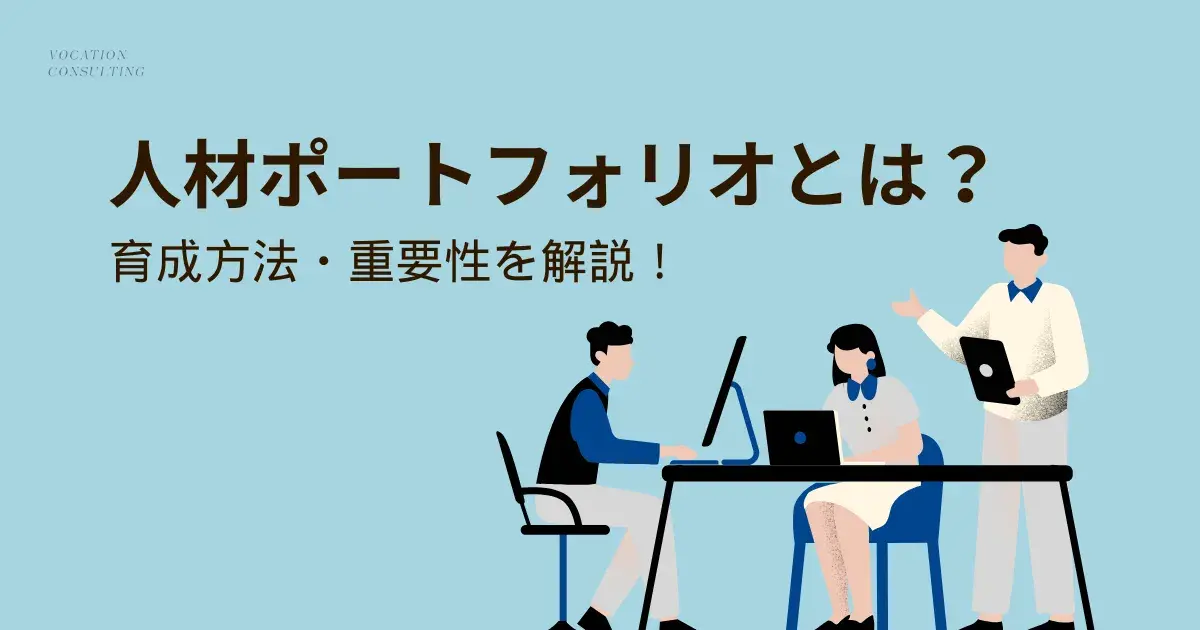従業員のやる気や定着率に直結する「ワークエンゲージメント」。その意味や測定方法、具体的な高め方をわかりやすく解説します。外部依存に頼らず、組織内で継続的に育てる“内製化支援”についてもご紹介します。
ワークエンゲージメントとは?
ワークエンゲージメントの定義(心理学・HR領域での意味)
ワークエンゲージメントとは、「仕事に対して前向きで充実した心理状態」のことを指します。具体的には、活力(Vigor)、熱意(Dedication)、没頭(Absorption)という3つの要素から構成され、仕事に対してやる気があり、意義を感じ、時間を忘れて取り組んでいる状態を意味します。
この概念は、オランダのユトレヒト大学の研究チームにより提唱され、現在では人事(HR)領域や心理学の分野で「健康的な働き方」を測る重要な指標として広く活用されています。
従業員満足度やモチベーションとの違い
しばしば「従業員満足度」や「モチベーション」と混同されがちですが、ワークエンゲージメントはより深い心理的関与を示す概念です。
| 指標 | 主な意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| 従業員満足度 | 会社や職場に対する満足感 | 受動的(満足していても仕事に熱心とは限らない) |
| モチベーション | 仕事への意欲・やる気 | 状況によって変動しやすい |
| ワークエンゲージメント | 仕事に対する活力・熱意・没頭 | 自律的・持続的な前向き行動を伴う |
つまり、エンゲージメントが高い人財は、会社に満足しているだけでなく、自ら行動を起こし、周囲にもポジティブな影響を与える存在です。
注目される背景(人的資本経営、健康経営、Well-being)
ワークエンゲージメントが注目される背景には、以下の3つの潮流があります。
1. 人的資本経営の強化
従業員を「資本」として捉え、その能力やモチベーションの最大化が企業価値に直結するという考えが広まり、企業はエンゲージメント向上に本格的に取り組むようになっています。
2. 健康経営へのシフト
心身の健康とエンゲージメントは密接に関係しており、離職防止や生産性向上の観点からも重要視されています。
3. Well-being(ウェルビーイング)の重視
働く人の「幸せ」や「充実感」を大切にする価値観が広がる中で、仕事そのものへのポジティブな関与が持続的な成長に不可欠とされています。
測定方法と代表的な指標
測定項目(活力・熱意・没頭など)
ワークエンゲージメントの測定は、以下の3つの心理的要素に基づいて行われます。
・活力(Vigor):エネルギッシュに働いている感覚、疲れにくさ
・熱意(Dedication):やりがい、意義を感じながら仕事に打ち込む姿勢
・没頭(Absorption):仕事に夢中になり、時間を忘れる状態
これらの要素がバランスよく高い状態にあることが、エンゲージメントが高い状態と定義されます。
主な測定ツール(例:UWES)
最も広く使われているのが「UWES(Utrecht Work Engagement Scale)」という診断ツールです。17項目(短縮版は9項目)に対して自己評価を行い、数値化されたスコアから個人・組織のエンゲージメント状態を可視化します。
日本企業でも多く導入されており、従業員アンケートなどに組み込まれていることもあります。
数値の見方と注意点
UWESなどのスコアは、各項目について「1〜7点」で評価され、平均点が高いほどエンゲージメントが高いとされます。
ただし注意すべき点は以下の通りです。
・高スコアでも一時的なことがある:プロジェクトへの熱中や残業過多による“過集中”状態をエンゲージメントと誤認しない
・スコアはあくまで“状態の一部”:スコアだけでは本質的な職場環境や人的関係は測りきれない
・部署や役職別に傾向を分析することが重要:全社平均だけでなく、組織ごとに違いを把握する必要がある
測定はあくまで手段であり、目的ではありません。測定結果をどのように捉え、どのように活かすのか、、つまりエンゲージメント向上につながる具体的なアクションにつなげることが大切です。
ワークエンゲージメントを高める具体施策
ワークエンゲージメントを高めるためには、単に「モチベーションを上げる施策」を打つだけでは不十分です。重要なのは、働く環境・関係性・成長機会・価値観といった複数の領域にアプローチし、組織全体で“前向きな働き方”を支える土壌をつくることです。以下では、実際に有効とされる具体的な施策を紹介します。
職場環境の改善(心理的安全性・裁量性など)
心理的に安心して意見を言える「心理的安全性」は、エンゲージメント向上の土台となります。
・否定されない環境:上司や同僚に対して“気兼ねなく発言できる”関係性があるか
・自律的な働き方:自分の仕事の進め方にある程度の裁量があるかどうか
こうした要素は、安心感や信頼感を生み出し、仕事への前向きな関与を後押しします。
キャリア支援とスキル開発
エンゲージメントが高い社員の多くは、「自分が成長している実感」を持っています。
・キャリア面談やコーチングを通じた中長期的な支援
・階層別・目的別の研修によるスキルアップ支援
・新しいチャレンジを任せる機会づくり
これらは「期待されている感覚」や「役割への納得感」を育み、組織とのつながりを強めます。
マネジメント・1on1の質向上
直属の上司との関係は、ワークエンゲージメントに最も強い影響を与える要素のひとつです。
・1on1ミーティングでの傾聴やフィードバックの質
・目標設定と業務支援のバランス
・部下の価値観や働きがいへの理解
マネージャーが「部下の成長と幸せ」に関心を持っているかどうかが、エンゲージメントの鍵を握ります。
組織文化づくりと理念浸透
最終的には、個別施策を超えて「自社らしい文化や価値観」の中にエンゲージメントが根づいている状態が理想です。
・ミッション・ビジョン・バリューを体現する行動の促進
・部門横断での理念共有ワークショップ
・従業員の声を活かす共創的な取り組み
単なる掛け声で終わらせず、「行動として浸透しているか」を評価軸にすることがポイントです。
よくある失敗と内製化の重要性
エンゲージメント向上に取り組む企業は増えていますが、「施策が形だけで終わる」「一時的な効果にとどまる」という声も少なくありません。その原因を見ていきましょう。
外部研修に頼りすぎる問題点
外部講師による研修やセミナーは、知識のインプットには有効ですが、以下のような限界があります。
・自社の課題にフィットしない内容
・一過性で終わる(継続しない)
・受講者任せで行動変容につながらない
つまり「実務に落ちないまま終わってしまう」ことが多く、効果が継続しにくいのです。
一時的なブーム施策で終わるリスク
エンゲージメントが注目されているからといって、流行りの施策だけを取り入れると、次のようなリスクが生じます。
・取り組みの目的が不明確で社員が戸惑う
・「またか」と冷めた反応が広がる
・数値の改善だけが目的化し、現場に負担がかかる
重要なのは、「なぜこれをやるのか」という意味づけと、一貫性ある実行体制です。
継続的な取り組みが難しい理由
エンゲージメント向上は“長期戦”です。しかし、現場では以下の課題がつまずきになりやすいです。
・担当者が変わると止まってしまう
・人事やマネジメント層に任せきりになる
・効果測定と改善が仕組み化されていない
こうした課題を解決するには、「自社で継続的に設計・実行できる体制=内製化」が不可欠です。
継続的にワークエンゲージメントを高めるためには、「ノウハウ」よりも「仕組みと習慣」が重要です。自社内でエンゲージメント向上施策を企画・実行できる体制づくりに関心がある方は、下記ページをご覧ください。
▶研修の内製化サポートはこちら
継続的なエンゲージメント向上の鍵は「内製化」
内製化とは?導入のメリットと実例
「内製化」とは、外部に頼らず、自社の中で施策や研修を企画・運用・改善していく仕組みを構築することです。
エンゲージメント施策においては、以下のようなメリットがあります。
・自社の文化や課題に合った内容を柔軟に設計できる
・社員の声を反映しながら改善サイクルを回せる
・外部依存から脱却し、継続的な取り組みが可能になる
たとえば、ある企業では、従業員サーベイの結果から浮かび上がった課題に対し、社内メンバーが主体となって研修企画・ワークショップ設計・振り返り支援までを行う体制を構築。現場の納得感も高く、数年にわたりエンゲージメントスコアの安定改善が実現しています。
社内で仕組みとして回る状態とは?
「仕組みとして回る」とは、属人化せずに以下の流れが自然に継続されている状態を指します。
1.課題発見:サーベイや面談から、現場の声を把握
2.企画設計:課題に応じた施策や研修を社内で立案
3.実行と運用:マネージャーや担当部署が現場に落とし込む
4.効果検証と改善:数値や声をもとに施策をブラッシュアップ
このように、一時的なイベントではなく、日常業務の中で自然に施策が育つ状態を作ることで、エンゲージメントは“維持”ではなく“向上”していきます。
研修内製化による人財育成と組織定着効果
研修の内製化は、単なるコスト削減の手段ではありません。人財の成長と組織の定着率向上という面でも非常に大きな効果をもたらします。
・研修を設計・実施する側の社員が成長する
・受講側も“自社ならでは”のリアルな学びを得られる
・「人を育てる文化」が組織に定着しやすくなる
つまり、内製化は「教える人」「学ぶ人」双方の当事者意識を高め、エンゲージメントの土壌をつくる中核的な仕組みです。
研修内製化サポートのご紹介
貴社の研修を“自社で企画・運用できる”体制に
外部研修の導入だけでは実現できない、“継続的な成果”につながる内製化支援を私たちはご提供しています。
・「現場の課題に合った研修を企画したい」
・「属人化せずに、運用を仕組み化したい」
・「人財開発を戦略的に強化したい」
そんなお悩みを持つ企業様向けに、自社でエンゲージメント施策を設計・実行できる状態をつくることを目的とした支援を行っています。
専門家による企画・設計支援
▶ 詳細はこちら:https://vc-corp.net/develop2
組織開発・人財育成の専門家が、貴社の目的や課題に応じて、以下のような支援を提供します。
・研修・ワークショップの企画設計
・ファシリテーター・講師向けの育成支援
・現場実装に向けた運用支援と定着化設計
サービスの特徴(企画設計・運用支援・継続伴走)
| 支援内容 | 特徴 |
|---|---|
| 企画・設計支援 | 自社の課題や人財像に合わせたカスタマイズ設計 |
| 運用・実装支援 | 社内運営マニュアル化・担当者育成をサポート |
| 継続伴走支援 | 月次相談・改善提案で自走化まで伴走 |
施策を「導入して終わり」ではなく、「続けられる仕組み」に変える支援を行っています。
ワークエンゲージメント向上は「習慣化」と「内製化」がカギ
ワークエンゲージメントは、一度の施策で完了するものではなく、日常的な関係性や行動の習慣化、組織文化の中で育つものです。そのため、短期的なイベントや外部依存の取り組みではなく、中長期の組織変革の一部として捉えることが重要です。
また、「この会社で働き続けたい」と社員が実感できる職場をつくるには、自社で企画・運用できる“内製化体制”の構築が不可欠です。エンゲージメントを“育て続ける”ことができる企業こそ、人的資本経営を実現し、人の定着・成長・長期活躍を生み出す組織を形づくることができるのです。