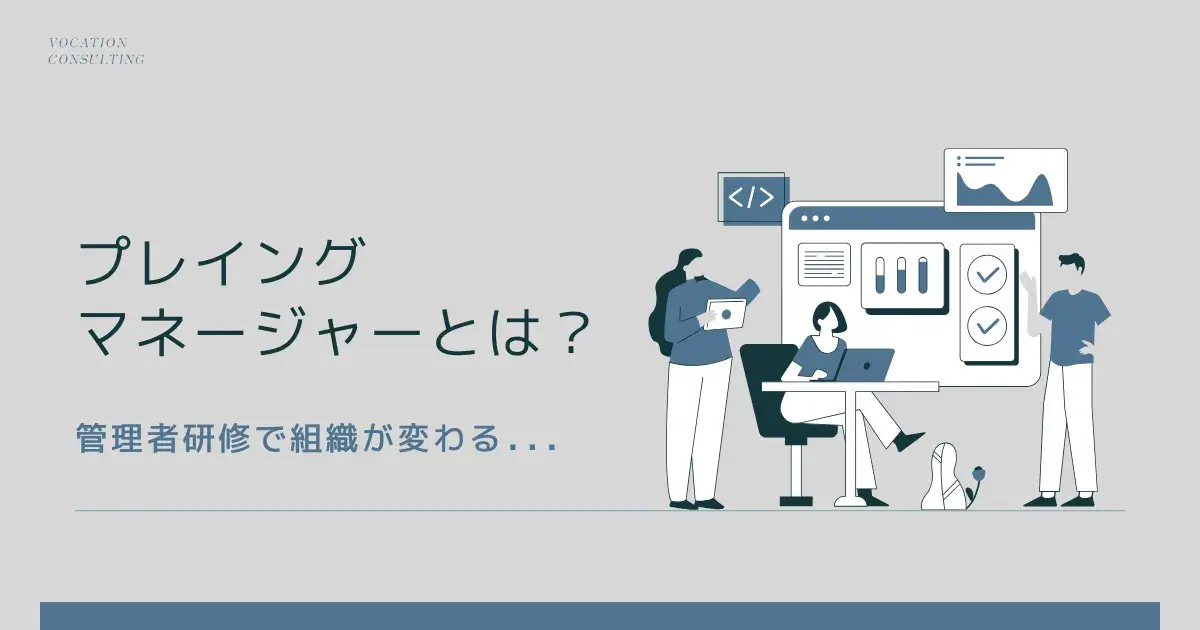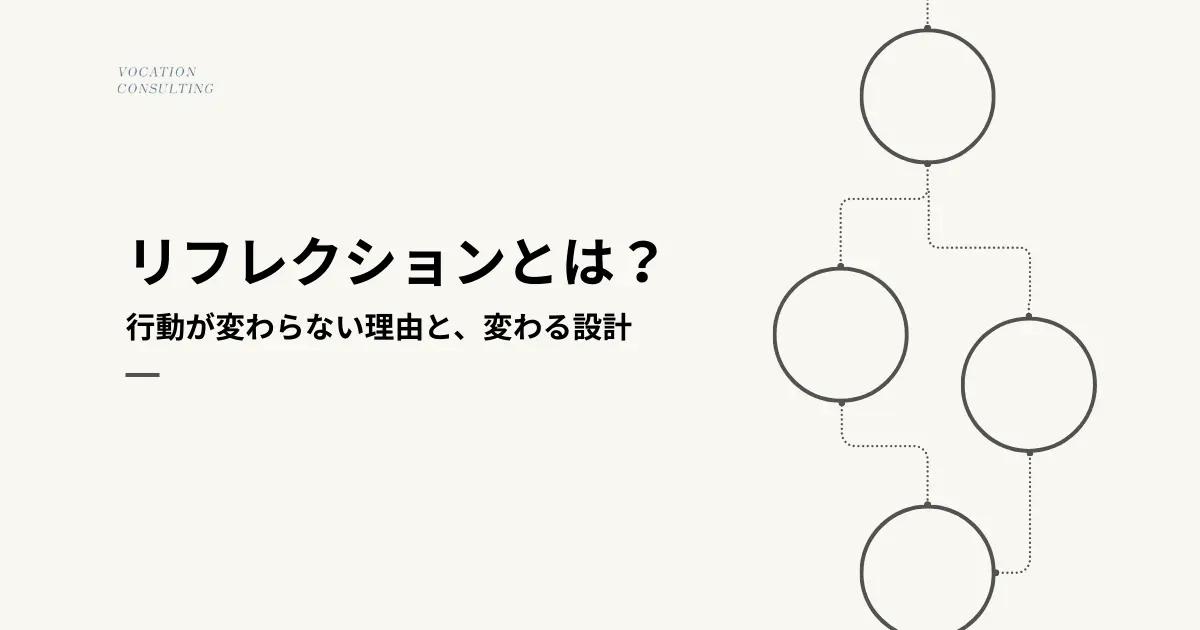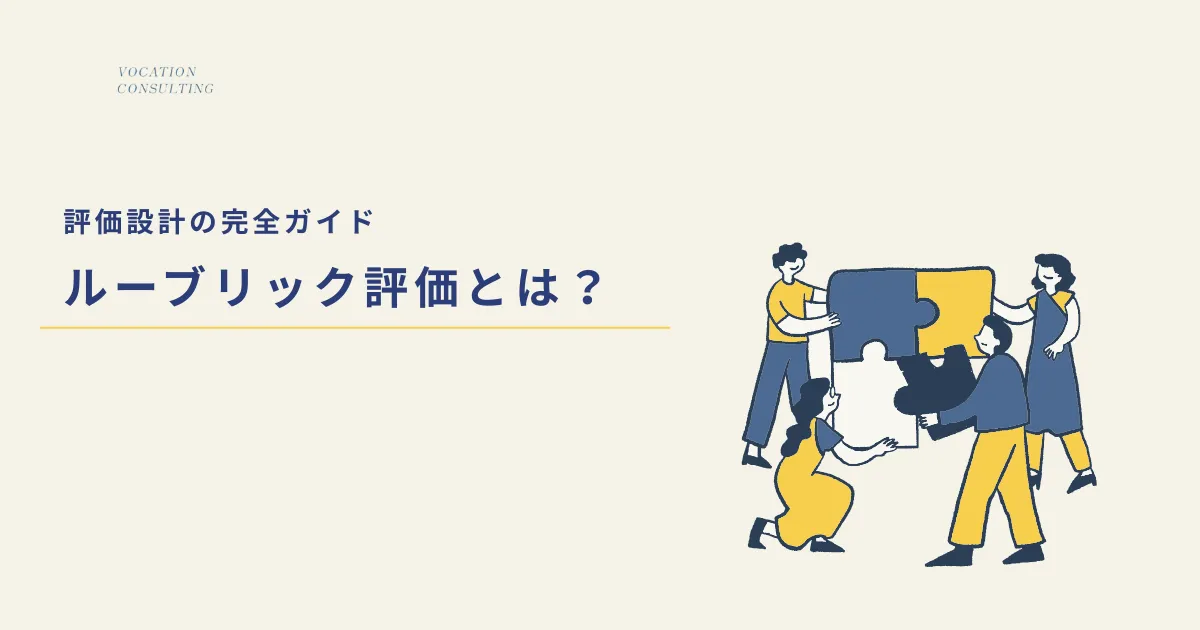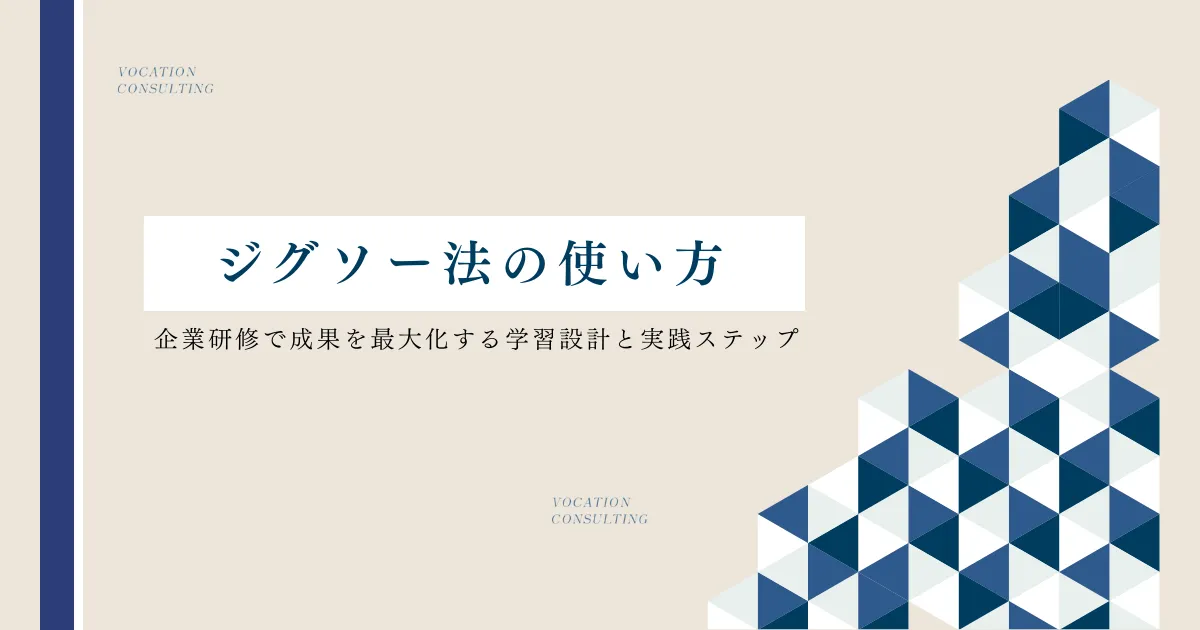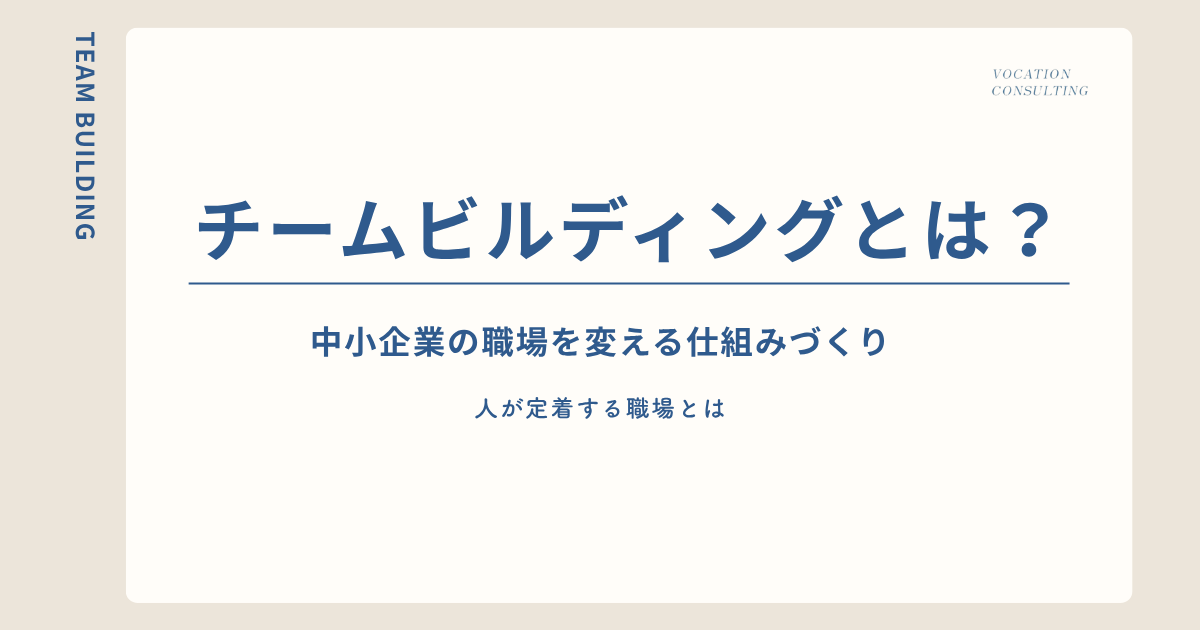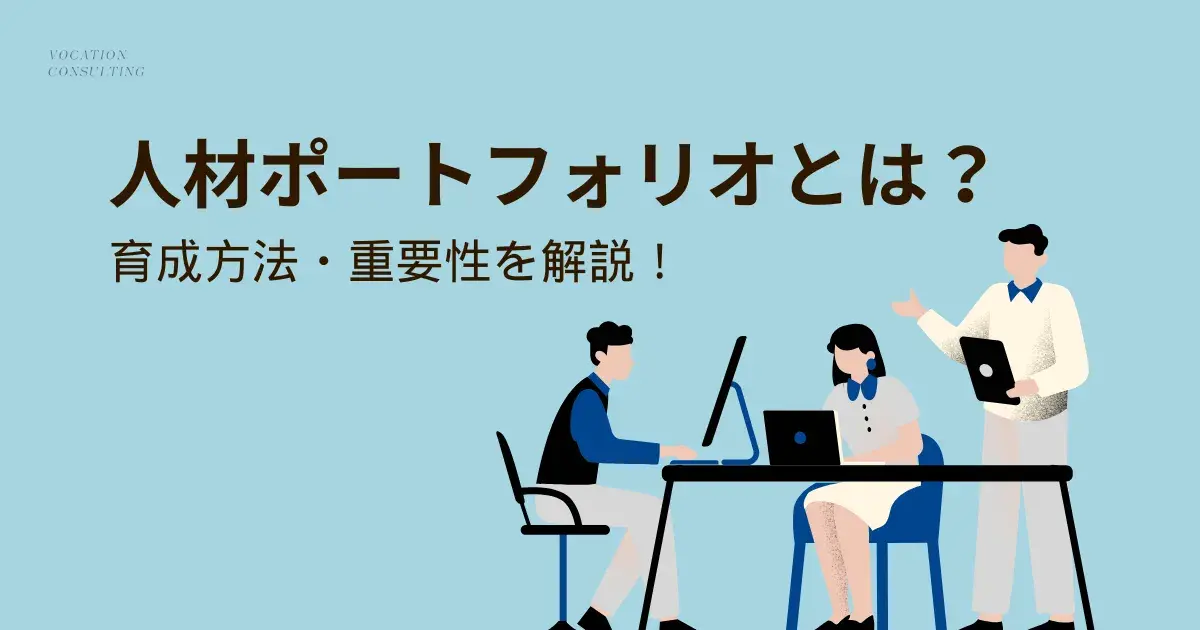プレイングマネージャーとは?役割と重要性をわかりやすく解説
現代の組織では「プレイングマネージャー(プレマネ)」という役職が急速に増えています。これは「プレイヤー(実務担当者)」として成果を出しながら、「マネージャー(管理職)」として部下をマネジメントするという、“二つの顔”を持つポジションです。
しかしその実態は「役割があいまい」「業務が過多」「育成が不十分」といった課題も多く、組織の中で“機能していない”ケースも少なくありません。
この記事では、プレイングマネージャーの定義・特徴から、一般的なマネージャーとの違い、役割のバランスまで、わかりやすく解説します。
プレイングマネージャーの定義と特徴
プレイングマネージャーとは何か?
プレイングマネージャーとは、自らも現場でプレイヤーとして業務をこなしながら、同時にチームや部下のマネジメントも担う役割のことです。
たとえば営業チームであれば、「自分も売上目標を持ちながら、メンバーの進捗管理や育成も行う」ようなポジションが該当します。
最近では中小企業やベンチャー企業だけでなく、大手企業でも人財・組織コストの最適化の一環として導入が進んでいます。
一般的なマネージャーとの違い
一般的なマネージャー(管理職)は、「プレイヤー業務を離れて、チームや組織のマネジメントに専念する」のが基本です。
一方、プレイングマネージャーはプレイヤーとして成果も出すことが求められるため、次のような違いがあります:
| 比較項目 | 一般的なマネージャー | プレイングマネージャー |
|---|---|---|
| 役割 | 管理・育成に専念 | 管理+実務の両立 |
| 業務範囲 | チーム全体の目標管理 | 自身の目標+チーム管理 |
| 評価軸 | チーム成果・定着度・成長度・生産性・成果・定着・成長・生産性などの向上に繋がる仕組みの構築 |
個人成果+チーム成果 |
このように、プレイングマネージャーは「二刀流の管理職」ともいえる役割を担っており、優れたバランス感覚が求められます。
プレイヤー業務とマネジメント業務の割合
プレイングマネージャーにとって大きな悩みとなるのが、「プレイヤー業務とマネジメント業務のバランス」です。
理想的には以下のような比率がよく言われます:
・プレイヤー業務:マネジメント業務 = 6:4〜5:5
・チームの成熟度が低い場合は、マネジメント比率を高める必要あり
・成果責任が強い環境では、プレイヤー業務が6〜7割になることも
しかし、実際の現場では8割以上がプレイヤー業務に割かれているケースも多く、マネジメントがおろそかになっているのが実情です。
このような状況では「部下の育成が進まない」「チームが自走しない」といった問題が表面化し、プレイングマネージャーの機能不全=組織課題へとつながります。
プレイングマネージャーの主な役割と現場の実態
プレイングマネージャーは、単なる「中間管理職」ではありません。現場で自ら成果を出しながら、チームのマネジメントも担うという、非常に高度な役割を求められるポジションです。
理想論ではなく、「実際の現場ではどうなっているのか?」という視点で、その実態を解説します。
業務遂行とマネジメントの両立
プレイングマネージャーの最大の役割は、“自ら成果を出しつつ、部下も育て、チームとして成果を最大化する”ことです。
これは以下のような複数の業務を同時に担うことを意味します:
・自身のプレイヤー業務(営業/開発/施策実行 など)
・チームメンバーの業務進捗・成果の把握
・目標設定とKPI管理
・部下の育成、フィードバック
・他部署との調整・報告
つまり、「短期成果のプレッシャー」と「中長期の組織づくり」の両立が求められるわけです。実務もこなしながら、部下の様子も常に気にかけ、上司には定期的に報告もする──
この構造自体が、非常に負荷の高い状態であることは想像に難くありません。
現場から見たプレイングマネージャーのリアル
現場で実際にプレイングマネージャーとして働いている人たちからは、以下のような声がよく聞かれます:
・「自分の仕事で手一杯で、部下に構う余裕がない」
・「育成やマネジメントの時間を取っても、それが評価に反映されない」
・「上司からは“数字を出せ”と言われ、部下からは“忙しすぎて頼れない”と言われる」
このように、“両方の期待を背負いながら、どちらの成果も問われる”という構造的ジレンマに陥っているケースが多く見られます。
加えて、「マネジメントの教育を受けずに現場の延長で任命される」ことも多く、正しいマネジメントの“型”が身についていないまま手探りでやっているのが現実です。
「成果を出しながらチームも見る」難しさ
そもそも、プレイヤーとして成果を出すには集中力とスピードが必要です。一方で、マネジメントには「聴く」「考える」「育てる」といった余白と視野の広さが求められます。
この“相反する思考とスタンスの切り替え”こそが、プレイングマネージャーの最も難しい点です。
・営業の数値が悪いから、自分で動いて契約を取る(プレイヤー思考)
・でも、その間に部下の相談には乗れず、育成が止まってしまう(マネージャー不在)
こうした状態が続くと、「チームは個人頼みで回るが、組織としては伸びない」という事態を招きます。
プレイングマネージャーを機能させるためには、「業務設計」や「評価制度」自体の見直しが必要不可欠です。単に「がんばれ」ではなく、組織側がサポート体制を整えることが求められています。
「きつい」「機能しない」と言われる原因とは?
プレイングマネージャーという役割は、現場とマネジメントの両方を担う重要なポジションです。しかし、多くの企業で「プレイングマネージャーが機能していない」「きつくて長続きしない」という声があがっているのも事実です。
なぜプレイングマネージャーは、これほどまでに“つらい役割”になってしまうのでしょうか?
業務過多と役割のあいまいさ
プレイングマネージャーは、「プレイヤー」と「マネージャー」の2つの役割を同時に担います。しかし、どこまでがプレイヤー業務で、どこからがマネジメントなのかが明確に定義されていないケースが多く見受けられます。
その結果、
・プレイヤーとしての成果も求められる
・チーム全体の進捗や育成も任される
・社内調整や報告も対応する
といった具合に、際限なく仕事が増え続けてしまうのです。本来は役割分担によって生産性を高めるはずが、役割のあいまいさによって逆に生産性が下がっている状況も少なくありません。
部下育成に時間が取れない
プレイングマネージャーの本質的な価値は、「チームの力を最大化すること」にあります。
しかし、現実には目の前の数字を追うことで精一杯になり、部下育成に十分な時間と労力を割けていないという声が多く聞かれます。
・「指導したいけど、自分の業務が終わらない」
・「気になる部下がいるが、関われずに後回しにしてしまう」
このような状態が続くと、部下は成長の機会を失い、マネージャーは「育成ができない自分」に自己嫌悪を感じることも。
結果として、チーム力もマネージャー本人のモチベーションも、双方が低下する悪循環に陥ります。
✔ 組織の中間管理職がうまく機能していないと感じるなら、それは“個人のスキル”ではなく“役割設計と育成環境”に問題があるかもしれません。
プレイングマネージャーが活躍できないのは、本人の努力不足ではなく、構造上の課題であるケースが多いのです。
上司・部下の板挟みによるストレス
プレイングマネージャーがもっともストレスを感じるのは、「上からのプレッシャー」と「下からの期待」の板挟みになる瞬間です。
・上司からは「数字を出せ」「もっと管理しろ」と指示され
・部下からは「忙しそうで相談できない」「頼れない」と不満を持たれる
このような立場では、どちらの期待にも応えようとして自分をすり減らしてしまうことが少なくありません。
しかも、プレイングマネージャー自身が孤独になりやすく、相談相手もいないことが多いため、結果的に離職やメンタル不調につながるケースも見られます。
プレイングマネージャーに求められるスキルとは?
プレイングマネージャーは、プレイヤーとマネージャーの両方の役割を担うハイブリッドなポジションです。 そのため、一般的な管理職よりも幅広く高度なスキルが求められます。
実務力とマネジメント力のバランス
まず前提として、プレイングマネージャーは「現場で結果を出す力」と「チームを導く力」の両方を求められる立場です。
・実務力:自ら売上を立てる、成果を出す、課題を解決する力
・マネジメント力:部下の目標管理、進捗把握、育成、評価などのチーム運営力
このバランスが崩れると、以下のような問題が起きます:
| 状態 | 問題点 |
|---|---|
| 実務に偏りすぎる | チームの育成が止まり、個人プレー頼みになる |
| マネジメントに偏りすぎる | 自らの成果が出せず、説得力や信頼が低下する |
プレイングマネージャーにとって最も重要なのは、「どちらかに偏らず、状況に応じて最適な役割を取れる柔軟性」です。
育成力・コミュニケーション力・時間管理
プレイングマネージャーは、プレイヤー時代には求められなかった“チームを動かす力”が必要になります。
①育成力
部下の強み・弱みを見極め、個々の状況に応じた指導・教育の選択+フィードバックを行う力。「自分ができること」と「教えられること」は別物であり、再現性ある育成の型を学ぶ必要があります。
②コミュニケーション力
上司への報連相、部下との信頼構築、他部署との調整など、関係性のハブとなる役割を担います。特に「部下が本音を話せる空気づくり」や「忙しくても話しかけやすい姿勢」が重要です。
③時間管理力
多忙な中で自分のタスクとチームマネジメントを両立するには、優先順位の判断やタスクの委譲も不可欠です。
「全部自分でやろうとしない」「手放す勇気を持つ」ことも、マネージャーとしての成長には欠かせません。
「放任でもマイクロマネジメントでもない」支援型マネジメント
プレイングマネージャーが陥りがちな落とし穴が、「任せきり=放任」か「細かく指示しすぎ=マイクロマネジメント」の両極端です。
・放任型:部下の進捗や状況が見えず、手遅れになるまで気づけない
・マイクロ型:部下が委縮し、自律的に動けなくなる
理想はその中間に位置する「支援型マネジメント」です。
支援型マネジメントの特徴は:
・目標や役割は明確に伝えた上で、プロセスはある程度任せる
・定期的にフォローや壁打ちの時間をつくる
・結果を責めるのではなく、結果に影響を与える行動を一緒に振り返る
・振り返りから気付きを生み出し、それを根拠に次の目標を一緒に考える
このスタンスで関わることで、部下は「見守られている」「頼れる」と感じ、自律性と安心感の両方を持って動けるようになります。
どう育てる?プレイングマネージャー育成の課題と解決策
プレイングマネージャーは、現場での実務と部下のマネジメントという二重の責任を担う立場です。しかし、多くの企業では「プレイングマネージャーが育たない」「いつまでも属人的で再現性がない」といった課題が生じています。
現場任せにしない「役割の明確化」
まず大前提として、プレイングマネージャーが機能しない最大の理由の一つが、「何を期待されているのかが曖昧」という点です。
・どこまでがプレイヤー業務?
・チームマネジメントはどの範囲まで?
・育成は「余裕があれば」なのか、正式な役割なのか?
このような曖昧な状態で任せても、マネージャーは判断基準を持てず、結果的に「やりすぎる or やらなさすぎる」という両極端になりがちです。
✔ 育成の第一歩は、プレイングマネージャーという役割そのものを“言語化”して明文化することです。役割が明確になれば、成果目標や評価基準も設定しやすくなり、「頑張っているのに報われない」状態を防げます。
「管理職研修」の重要性と投資効果
多くの企業では、「プレイヤーとして優秀だから」という理由でマネージャーに昇格させるケースが一般的です。しかし、実務スキルとマネジメントスキルはまったく別物です。
優秀なプレイヤーも、以下のような“未経験領域”に直面します:
・部下の育て方がわからない
・フィードバックがうまくできない
・チーム運営や会議設計のやり方を知らない
ここで必要なのが、マネジメントの“型”をインストールする「管理職研修」です。
管理職研修では、以下のような即実践できるスキルを体系的に学べます:
・目標設定とKPIマネジメント
・1on1や育成面談の進め方
・支援型マネジメントの実践方法
・チームが動くコミュニケーション設計
✔ 研修を通じて“仕組みとしてのマネジメント”を学ばせることで、属人的なやり方から脱却し、再現性のある組織運営が可能になります。
プレイングマネージャーが変わると組織はどう変わる?
育成されたプレイングマネージャーが現場で機能し始めると、組織には以下のようなポジティブな変化が生まれます:
・部下が成長し、マネージャーの手が空く(任せられる環境)
・「管理者1人頼み」から「チームで成果を出す構造」へ
・離職率やモチベーション低下の要因が減る
・現場が自走し、上層部の負担も減る
つまり、プレイングマネージャーの育成は、一人の人財強化ではなく「組織改革の起点」となりうるのです。
プレイングマネージャーの悩みを“仕組みで解決”したい方へ
「プレイヤーとしては優秀」でも、「マネージャーとしては機能しない」──そんな人財を放置していませんか?
✔ マネジメントの“型”をインストールするだけで、現場は自走し始めます。
✔ 評価制度・育成設計・実践トレーニングまで一気通貫で支援します。
→ 管理者育成プログラムはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. プレイングマネージャーは本当に必要なのでしょうか?
はい、プレイングマネージャーは組織の規模やステージによっては非常に有効なポジションです。
特に以下のような状況では、プレイングマネージャーが機能しやすい傾向にあります:
・メンバーが少数精鋭で、全員が実務に関わる必要がある
・成果に直結するプレイヤーとしての経験・実績が重要視される
・プレイヤーからマネージャーへの「移行期」を支える必要がある
一方で、中長期的には「プレイング比率を下げ、マネジメントに専念できる体制」への移行が望ましいとされています。
つまり、プレイングマネージャーは「永続的な役割」ではなく、「移行期や成長過程での一時的な役割」として設計するのが理想です。
Q2. 組織によって適正な役割比率はありますか?
はい、プレイングマネージャーの「プレイヤー業務」と「マネジメント業務」の理想的な比率は、組織の規模・チームの成熟度・事業フェーズによって異なります。
以下に一般的な目安を示します:
| 組織・状況 | プレイヤー:マネジメントの比率(目安) |
|---|---|
| 小規模チーム(5人以下) | 7:3(プレイヤー業務が中心) |
| 成長フェーズの中規模チーム | 5:5(両立バランスが必要) |
| 組織化が進んだチーム | 3:7 または マネジメント専任 |
重要なのは、「どちらをやるか」ではなく、「今、どちらを優先する必要があるのか」を見極めて役割を再設計することです。
Q3. プレイングマネージャーに向いている人の特徴はありますか?
プレイングマネージャーに向いている人には、以下のような特徴が見られます:
・自分で成果を出すだけでなく、他人の成長にも喜びを感じられる
・短期と中長期、両方の視点で物事を考えられる
・責任感が強く、チーム全体の成果にコミットできる
・忙しくても人の話を聴く余裕を持てる
・「自分でやった方が早い」から脱却し、任せることに価値を感じられる
ただし、こうした資質は“もともと備えている人”よりも、経験と教育によって育つケースが多いものです。
したがって、向き・不向きよりも「育成の仕組みがあるかどうか」が、プレイングマネージャーを成功させる鍵となります。