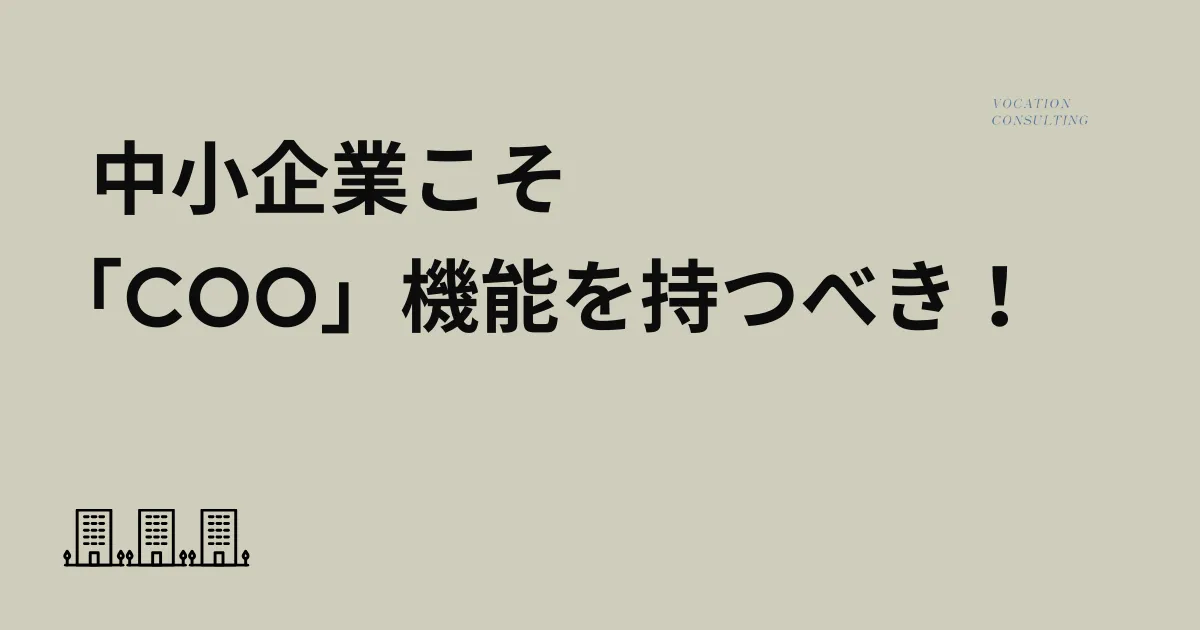日本の中小企業では、「COOを採用すべきかどうか」という悩みが増えています。
しかし実際には、COOという役職そのものが本質ではありません。多くの企業で欠けているのは“COOという人”ではなく、事業を前に進めるための「COO機能」です。売上が伸び悩む、組織が混乱する、優先順位が毎月変わる –
これらの問題の背景には、経営と現場の間に「戦略を翻訳し、現場を動かす役割」が存在しないという共通点があります。
本記事では、これまでの記事で触れていない“COO機能”という切り口から、企業の成長を支える実務的な仕組みづくりを解説します。
COOを役職として理解すると、なぜ失敗するのか
日本でCOOが誤解されやすい理由は、「役職名」として導入されがちだからです。
しかしCOOは本来、経営と現場を橋渡しする“機能”を担います。経営者が描いた戦略が現場で実行され、現場で起きている事実が経営判断に反映される – 。
組織が成長するほど、この翻訳機能が欠かせなくなります。ところが中小企業の場合、この役割が曖昧なまま、
「右腕が欲しい」
「自分の代わりに指示してほしい」
などの期待だけが先行し、COOを役職として採用してしまうケースが多くあります。
すると次のようなズレが起きます。
- COOは経営者が期待するほど現場を動かせない
- 戦略が“言葉だけ”で終わる
- 改善がプロジェクト化されず、結局経営者が全部やることになる
これは、COOの“肩書き”ではなく、「どの機能を組織に導入したいか」が定義されていないことが原因です。
COO機能が欠けている会社で必ず発生する“3つの詰まり”
COOを採用していなくても、COO機能が機能していない会社には、ある共通点があります。それは「詰まり」を抱えているということです。
1つ目の詰まりは、戦略と現場が分断されることです。
経営者の頭の中には明確な戦略があっても、現場側は別の優先順位で動いてしまい、両者が噛み合わなくなる状況が発生します。これが続くと、施策は空中戦のまま終わり、社内会議は形骸化し、改善サイクルが回らなくなります。
2つ目は、数値管理がブラックボックス化することです。
指標は存在しても、誰がどの数字に責任を持つのかが曖昧なため、数字が「状況報告の材料」になってしまいます。数字をもとに意思決定する組織ではなく、数字を“読むだけ”の組織になるのです。
3つ目は、組織が属人化し再現性がなくなることです。
標準化された業務フローがないと、人が辞めた瞬間に事業が止まり、新人育成の負荷が高くなります。優秀な人が“穴埋め役”になり、採用しても戦力化できないという典型的なスパイラルに陥ります。
この3つの詰まりこそ、COO機能が存在しないことの証拠です。
COOは“4つの機能”に分解できる:役職より機能を入れる方が正しい
中小企業がいきなりCOOを採用する必要はありません。むしろCOOの役割を分解し、会社に足りていない機能だけを取り入れるほうが現実的です。
COO機能は次の4つに整理できます。
① 戦略翻訳機能(経営の意図を現場の言語に変換する機能)
COOが果たす最も重要な仕事は、経営者が描く戦略を現場が実行できる形へと翻訳することです。
たとえば「今期は新規顧客を増やしたい」と経営者が言ったとします。しかしこれだけでは現場は動けません。
- どのチャネルを伸ばすのか
- そのためにどの指標を改善するのか
- どの部署と連携する必要があるのか
こうした戦略の“構造化”こそが戦略翻訳機能です。
② 事業推進機能(戦略を動かす仕組みをつくる機能)
戦略を言葉で伝えるだけでは事業は動きません。優先順位を決め、プロジェクト化し、期限を設定し、進捗を管理することで、はじめて戦略は“動くもの”になります。
事業推進機能が入ることで、企業は「やること」だけでなく、「やらなくていいこと」が明確になります。これは中小企業にとって非常に大きなメリットです。
③ オペレーション設計機能(業務の標準化・再現性づくり)
組織が小さいうちから必要になる機能です。ある程度の売上規模になると、業務が複雑になり、人の力だけで回すのが限界を迎えます。
- 営業フロー
- 顧客対応フロー
- 社内業務の標準化
- 引き継ぎの仕組み
こうしたオペレーション設計は、COO機能として導入することで初めて“維持できる組織”に変わります。
④ 数値管理機能(KPIをモニタリングし改善する機能)
COO機能の中でも、最も効果が目に見えやすいのが数値管理です。
- 誰がどの数字に責任を持つか
- どの数字を改善すべきか
- 異常値が出たらどう対応するか
数値管理機能が動き出すと、会議の質が劇的に変わります。共有会議から、「意思決定と改善」のための会議へと進化するのです。
今日から始められる“COO機能インストール”の5ステップ
COO機能は、必ずしも人を採用する必要はなく、会社に合わせて小さく導入できます。以下に、中小企業が今日から取り組める5つのステップを紹介します。
STEP1:まずは事業の詰まりを正確に棚卸しする
どの企業でも最初にやるべきことは、現状把握です。経営者が感じている課題と、数字で見える課題が異なることは非常によくあります。
- 集客導線はどこが弱いのか
- 成約率はどの段階で落ちているのか
- 単価やリピートはどこに課題があるのか
こうした「構造的な把握」がCOO機能導入の出発点です。
STEP2:改善すべき“ボトルネック”を一つに絞る
中小企業はリソースが限られているため、課題を同時に解決しようとすると失敗します。最初にやるべきは「1つだけ選ぶ」ことです。
例えば、
- リードは十分だが営業が弱い
- 単価が低い
- CS負荷が高い
経営者が悩む問題のなかで、最も売上インパクトが大きいものを優先します。
STEP3:COO機能の“最小ユニット”を導入する
いきなり役職化する必要はありません。まずは小さく、会社に適した形で導入します。
- 週1の事業レビュー会議
- 主要なKPIのダッシュボード化
- オペレーションの簡易マニュアル化
この最小ユニットだけでも、組織の動きは大きく変わります。
STEP4:経営と現場の“週次PDCA”を回す
週次で課題と改善を話し合う習慣が生まれると、COO機能は自然と育ちます。
週次会議で見るべきは「数字」ではなく、数字から見える“動くべきポイント”です。
改善テーマを毎週設定し、次週に振り返る。
このリズムが企業の成長速度を決定づけます。
STEP5:機能が定着した段階で、COOを置くかどうか決める
最後に役職化を判断します。
ここではじめて、
「専任のCOOが必要か?」「外部の支援で十分か?」が明確になります。
最初から役職にしないほうが成功率は高まります。
外部パートナーとして“COO機能”を導入するという選択肢
最近増えているのが、いわゆる“Fractional COO(パートタイムCOO)”の形での導入です。
これは、フルタイム採用ほどのコストをかけず、必要な機能だけを外部から導入するモデルです。社内にCOO候補がいない会社でも、COO機能自体は導入できます。
特に、
- 経営者が現場から離れられない
- 部門間の連携が弱い
- 数値管理ができていない
- 事業スピードが不安定
といった企業には非常に相性が良い方法です。
まとめ:小さな会社こそ“COO機能”が成長の壁を超える鍵になる
COOは「採用するかしないか」だけの議論ではありません。会社が成長を続けるためには、戦略を現場の言葉に翻訳し、事業を前に進める仕組みをつくることが欠かせません。その中核となるのが、戦略翻訳、事業推進、オペレーション設計、数値管理という4つのCOO機能です。
この4つの機能が自社の中で動き出したとき、改善のスピードは格段に高まり、成長のブレーキになっていたボトルネックが一つずつ外れていきます。中小企業であっても、いきなり役職を増やす必要はありません。
まずは自社に合った最小単位からCOO機能を取り入れ、成長の土台を整えることが次のステージへの一歩になります