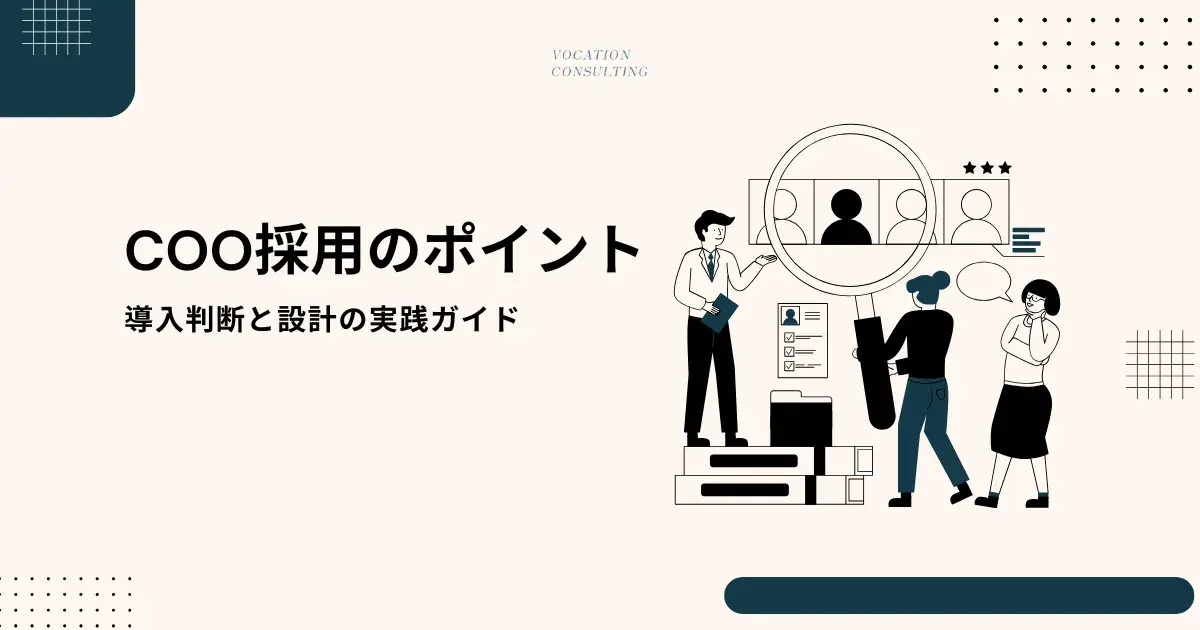COOを採用したのに期待通りに機能しない – その原因は、候補者ではなく“組織側の準備不足”かもしれません。本記事では、COOが機能しない企業に共通する誤解や、導入前に整えるべき設計、経営者に求められるマインドまでを具体的に解説します。
COOが“機能しない企業”とは?
COO(最高執行責任者)は、組織の実行力を高め、経営の地に足をつけるための重要なポジションです。しかし、実際には「採用したけど期待通りに機能しなかった」という声も少なくありません。その多くは、役割への誤解や組織構造とのミスマッチに起因しています。
ここでは、COOがうまく機能しない企業に共通する3つの誤解を紹介します。
社長の「右腕ほしい病」が招く人選ミス
よくある失敗の1つが、社長が「とにかく信頼できる人に任せたい」という思いから、「右腕がほしい」という感覚だけでCOOポジションを作ってしまうケースです。
この場合、職務設計も評価指標も曖昧なまま採用が進み、結果的に「何を任せていいかわからない」「期待と現実のギャップが大きい」といったズレが生まれます。COOは感覚で配置する役職ではなく、明確なミッションと構造上の必要性があってこそ機能するポジションです。
「万能プレイヤー」的期待で失敗する典型パターン
COOに「経営も現場もわかって、全部やってくれる人」という万能型の期待を抱いてしまうと、ほぼ確実に失敗します。なぜなら、COOの本質は「全体を動かす構造を設計・運用する役割」であり、万能型プレイヤーではないからです。
経営と現場の両方を見られることは重要ですが、「何を、どこまで任せるのか」が決まっていないままに、あらゆる業務を背負わせてしまうと、機能不全と疲弊を招きます。
「管理職の延長」で任せる危険性
社内の優秀なマネージャーをそのままCOOに昇格させるケースも多いですが、これは危険をはらみます。管理職とCOOはまったく別物の役割です。
管理職は「与えられた目標を部下とともに達成する」のが仕事ですが、COOは「戦略を実行可能な構造に落とし込み、全社を横断して推進する」存在です。全社視点・構造設計・横断的統制といった観点が欠けていると、COOとしての機能は果たせません。
「自社にCOOは必要か?」を判断する5つの問い
COOを採用するかどうかは、単なるポジションの有無ではなく、自社の経営構造や成長段階との整合性によって決まります。以下の5つの問いに答えることで、COOが本当に必要な状況かどうかを診断してみましょう。
① 社長が本来集中すべき業務は何か?
社長が営業、開発、採用、バックオフィスなど、あらゆる業務に関わりすぎていないでしょうか?
本来、社長が注力すべきは「戦略設計」「外部折衝」「資本政策」など、未来をつくる業務です。これらが疎かになっているなら、戦略実行の担い手=COOの検討余地が出てきます。
② 現場が戦略を実行できていない原因は?
戦略はあるのに、現場が動かない・浸透しないという状況はありませんか?これは多くの場合、“実行設計の空白”が原因です。COOは、戦略を現場に橋渡しし、ボトルネックを見つけ、組織に落とし込むプロフェッショナル。実行責任者が不在なら、COO導入の余地があると言えるでしょう。
③ 社内にCOOの受け皿(役割設計と権限構造)はあるか?
「採用したはいいけど、どこまで任せればいいかわからない」という状態ではCOOは機能しません。
職務領域・権限範囲・意思決定のプロセスなど、COOの役割を受け止める組織構造がなければ、誰を採用しても機能不全になります。
④ 評価指標(KPI)を明文化できるか?
COOに期待する成果や行動があいまいだと、評価も育成もできません。
たとえば、「離職率の改善」「事業部間の連携強化」「利益率の向上」など、数値化された目標を持てるかどうかが、COO採用の前提条件になります。
⑤ 経営チームとしての連携体制を整備できるか?
COOは単独で機能する役割ではありません。CEOやCFO、他の幹部と横並びで戦略と組織を共に担う存在です。
「経営チームとしての意思決定と連携ができる体制」が整っていなければ、COOが浮いた存在になり、結果的に退職・組織混乱を招くこともあります。
この5つの問いを通じて見えてくるのは、「COOが必要か」ではなく、“COOが機能する土壌があるか”という視点です。COOは単なる人財配置ではなく、「経営の再設計」です。
もし上記の問いに明確に答えられない場合は、採用の前に組織構造や役割設計を整理する支援を検討することも、有効な選択肢になるでしょう。
COO導入前に準備すべき3つの設計
COOの採用は、単なるポジション補充ではなく、経営構造の再設計です。
「なんとなく必要そうだから」「信頼できる人がいたから」といった曖昧な理由で導入すると、高確率で機能しなくなります。
その失敗を未然に防ぐには、採用前の設計段階が極めて重要です。ここでは、COOを迎える前に必ず整えておきたい3つの設計要素を紹介します。
① ミッション設計(何を成功させたらCOOとして評価されるか)
まず必要なのは、「COOとして、何を達成すれば成功とみなすのか?」というミッションの明確化です。
たとえば以下のように、成果の定義が曖昧だと、採用後に評価軸がブレます:
- 「なんとなく業務を任せたい」
- 「現場のマネジメントを強化してほしい」
- 「社長の右腕になってくれればいい」
これでは、COO本人も、周囲の組織も、何を軸に動けばいいかわからない状態になります。逆に、「3ヶ月以内に営業プロセスを標準化する」「6ヶ月で事業部間の連携スキームを再設計する」など、定量目標・行動目標が設定されていると、採用後も成果を可視化しやすくなります。
② 組織上のポジションと意思決定フロー
COOを迎えるにあたって、組織図上の位置づけと、意思決定権限の明確化は必須です。
「誰の下に位置し、誰と並び、どの範囲において決定権を持つのか?」が曖昧だと、社内での立場が不安定になり、最悪の場合は現場と対立構造を生む原因にもなります。
また、以下のようなフローの整備も重要です:
- COOが決められる範囲はどこまでか?
- CFO・CTO・事業部長との優先順位や調整ルールは?
- 緊急時の意思決定プロセスはどうするか?
任せたいのに任せられない、責任はあるのに権限がないという状態を防ぐためには、権限と責任の線引きがセットで設計されている必要があります。
③ CEO・他CXOとの役割の線引き
COOの機能は、CEO・CFO・CHROなど他のCXOと密接に連携して発揮されるものです。だからこそ、「誰が何を担当するのか」を明確にしておかないと、業務の重複や衝突が発生します。
たとえば、以下のような視点で役割を分解しておくと、混乱を避けやすくなります:
- CEO:戦略・外部折衝・資本政策・長期ビジョン
- COO:戦略の実行設計・部門横断の統制・ボトルネック改善
- CFO:資金管理・予実管理・投資判断
このように、「自社におけるCXOの業務地図」を作っておくことで、COO導入後も組織が円滑に機能する基盤が整います。
COOの役割を“機能別”に再定義する
「COO」とひとくちに言っても、企業ごとに求められる役割は大きく異なります。それにもかかわらず、「万能型COO」を求めて失敗するケースが後を絶ちません。
ここでは、COOの機能をタイプ別に再定義し、自社にとって必要なCOO像を明確にするための視点を紹介します。
実行系COO/改革系COO/統合系COOの違い
| タイプ | 主な役割 | 向いている企業フェーズ |
|---|---|---|
| 実行系COO | 既存戦略の現場展開・運用・KPI管理 | 拡大期・業務スケール局面 |
| 改革系COO | 部門再編・業務改善・生産性向上 | 混乱期・業績悪化・再建期 |
| 統合系COO | 複数事業/拠点のマネジメント統合 | 多角化・PMI・グループ再編期 |
COOの役割を「万能」ととらえるのではなく、企業課題に合った“特化型”の機能として設計することが重要です。
自社に必要な“タイプ”を見極める視点
自社に必要なCOOを見極めるには、まず以下の問いに答えてみてください:
- 戦略はあるが、現場が動けていない → 実行系?
- 現場がバラバラで、生産性が低い → 改革系?
- 事業が増えすぎて統制できない → 統合系?
このように、課題起点でCOOの機能を設計することで、採用後のミスマッチや不信感を防ぐことができます。
採用要件は「万能型」ではなく「特化型」で設計する
COOを採用する際、「全部できる人」を求めてしまうと、現実的な人財像がぼやけてしまいます。
むしろ、「この分野で実績を出してきた人」「この課題を任せられる人」という形で、“課題に対する解決力”に絞った要件定義をする方が、候補者とのミスマッチも起きにくくなります。
COO採用が成功する企業の“経営者マインド”とは?
COOの採用は、「信頼できる人に任せたい」という感情だけで進めてしまうと、思わぬ失敗を招くことがあります。
実は、COO導入がうまくいくかどうかは、候補者の能力以上に、経営者自身のスタンスや覚悟に大きく左右されるのです。ここからは、COO採用を成功に導くために必要な「経営者マインド」の3つのポイントを解説します。
自分の業務の一部を明け渡す覚悟
多くの経営者にとって、会社は「自分の分身」とも言える存在です。
特に創業期や少数精鋭の組織では、営業・採用・開発・資金調達など、あらゆる業務を社長自身が担ってきたケースも多いでしょう。
しかし、COOを迎えるということは、これまで自分が直接見ていた業務を「任せる」ことになります。つまり、“手放す覚悟”がなければ、COOは機能しないのです。
「任せたけどやっぱり口を出してしまう」「権限を与えたつもりが、承認待ちで動けない」──こうした状態では、どんなに優秀なCOOでも力を発揮できません。
COOを採用する前に、「何を手放すのか」「どこまで任せるのか」を明確にし、経営者自身が変わる準備をしておく必要があります。
組織視点と成果基準で任せる力
COOは、単なる“部下”ではなく、「経営チームの一員」として位置づけられる存在です。
だからこそ、「自分が指示を出して動かす」関係ではなく、「成果に向けて役割を分担する」スタンスが求められます。重要なのは、“人ではなく構造で任せる”こと。
たとえば「営業を任せる」ではなく、「営業利益率を改善する仕組みづくりを任せる」といったように、成果と責任を構造で整理した上で任せることで、COOは初めて自走できるようになります。
任せるとは、「業務を丸投げすること」ではなく、「目標を明確にして権限を委ねること」。この視点に立てる経営者こそ、COOとともに経営を飛躍させることができます。
「人柄重視」だけに依存しない判断軸
「信頼できる人に任せたい」「長年の知人だから安心」という理由でCOOを選ぶケースは少なくありません。もちろん、信頼関係は重要な要素ですが、それだけに依存するのは危険です。
COOに求められるのは、経営視点での課題解決力・組織マネジメント力・戦略実行力など、非常に高度なスキルです。いくら人柄が良くても、それが現実の課題に対応できなければ、組織にとってはマイナスになります。
大切なのは、「信頼できるかどうか」ではなく、「構造を任せられる能力があるか」「期待する成果を出せるか」という判断軸を持つこと。
感覚ではなく、役割設計と成果基準に基づいた採用基準を設けることで、COOとの関係も健全で持続可能なものになります。
COOを採用する前に“組織の受け皿”を整えよう
COO採用で最も重要なのは、「誰を採るか」よりも、「どう機能させるか」です。
そのためには、以下のような“受け皿”を事前に整備しておくことが欠かせません:
- COOの役割とミッションの明確化
- 任せる業務範囲と意思決定のルール設定
- 他CXOとの役割分担と評価基準の設計
これらが曖昧なまま採用すると、組織内の混乱や早期離脱のリスクが高まります。
もし、どこから手をつければよいかわからない場合は、導入前コンサルティングの活用も有効です。社内の課題を可視化し、最適なCOO像と機能設計を明確にすることで、採用の失敗を防げます。
【ご相談受付中】
「COOが必要かどうか悩んでいる」
「過去に採用でうまくいかなかった」
そんな企業様に向けて、COO像の明確化・設計・採用支援までを一貫サポートいたします。
まずは、無料相談で現状の整理からお気軽にご相談ください。
▶︎【無料相談はこちら】貴社に最適なCOO像の明確化・採用設計をご希望の方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。