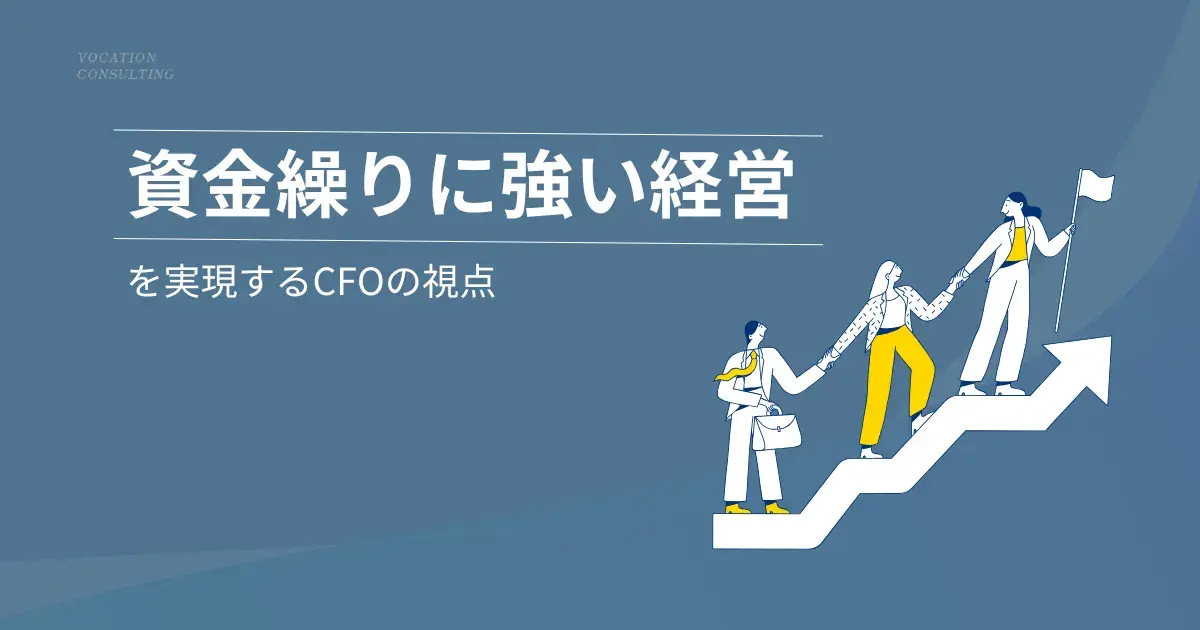経営が順調なのに、なぜか手元にお金が残らない -そんな悩みを抱える中小企業は少なくありません。実は“財務の見える化”ができていないことで、黒字倒産や資金ショートのリスクが潜んでいるのです。
本記事では、資金繰りに強い経営を実現するためのCFOの視点と役割を解説します。
資金繰りに強い会社は「未来予測」に強い会社
財務不在経営の危険性とは?
多くの中小企業では、経営者が売上や利益の数字だけを見て経営判断を下しているケースが少なくありません。しかし、「財務の視点」が抜け落ちた経営は、いわば“計器のない飛行機”のようなものです。
現預金の動き、借入の返済スケジュール、入出金のタイミングを把握していなければ、黒字倒産や資金ショートといったリスクは常に隣り合わせ。どれだけ商品やサービスが優れていても、資金繰りに失敗すれば会社は前に進めません。
「利益が出ているのに現金がない」現象の正体
経営者からよく聞かれる悩みに「利益は出ているはずなのに、手元にお金が残らない」というものがあります。これは、会計上の利益と実際のキャッシュフローが一致しないことに起因しています。
例えば、売上が立っていても未回収の売掛金が多ければ、現金は手元にありません。また、設備投資や借入返済など、損益計算書には表れない出費が現金を圧迫することもあります。
こうしたズレを理解し、未来の資金繰りを予測・管理する体制がなければ、突発的な支払いに対応できず、経営リスクが一気に高まります。資金繰りに強い会社とは、単に“お金がある会社”ではなく、お金の動きを先読みできる会社なのです。
CFOの役割は“数字を読んで未来を変える”こと
単なる経理・管理会計ではなく「経営戦略パートナー」
CFO(最高財務責任者)と聞くと、大企業の専任ポジションというイメージを持たれるかもしれません。しかし、いま中堅・中小企業にこそ、“財務を武器にした戦略的経営”を実現する右腕としてCFOの役割が求められています。
経理や管理会計は、過去の数字を「記録・報告」する役割にとどまります。一方でCFOは、そこから得られるデータをもとに、未来のキャッシュフローを予測し、投資判断や資金調達の戦略を設計する存在です。
つまり、CFOとは「数字を読む」だけでなく、「数字で未来を変える」パートナー。社長とともに経営の意思決定を行い、会社の持続的成長に直結するアクションを支える存在なのです。
✔ CFOの具体的な役割やスキルについては、こちらもご覧ください
→CFOの基礎的な役割はこちら
CFOが構築する3つの「財務の見える化」
月次着地予測(PL・BS・CF)
CFOが最初に着手するのが、月次決算ベースでの着地予測(損益計算書:PL、貸借対照表:BS、キャッシュフロー計算書:CF)の仕組み化です。
単なる過去データの集計ではなく、売上・原価・固定費の動きをもとに「今月・来月・半年後の利益・資金繰り」をシミュレーションすることで、経営者は資金不足を事前に察知し、早めの対策が可能となります。
KPIダッシュボード(経営に必要な指標の可視化)
CFOは、経営に直結する重要指標(KPI)を整理し、“一目で会社の健康状態がわかるダッシュボード”を構築します。
売上・利益率・回収期間・在庫回転率などの数字をリアルタイムで可視化することで、経営陣は勘や経験ではなく、データに基づいた意思決定を行えるようになります。
資金繰り表と借入管理の自動化
資金繰りの把握は、会社の「血流」を把握することと同じです。CFOは、入金・出金のタイミングを一覧化した資金繰り表を自動化し、借入返済や追加融資の最適なタイミングを提案します。
これにより、「いつ・いくら資金が不足するか」が事前に見えるため、資金ショートのリスクを大幅に減らせます。
CFOがいない企業に起きる“3つの落とし穴”
経営判断の遅れ
数字を整理し分析する人財がいなければ、経営者は「感覚頼りの判断」をせざるを得ません。市場変化や資金状況を先読みできず、投資や人員計画が後手に回ることが多くなります。
キャッシュの誤管理
利益が出ていても、キャッシュフローが悪化して倒産する企業は少なくありません。CFO不在の企業では、資金繰りを正しく把握できず、借入・支払・回収のバランスが崩れることが大きなリスクとなります。
投資と資金調達のバランス崩壊
新規事業や設備投資を進める際、CFO不在の企業は「投資金額に対してどれだけの資金調達が必要か」を計算しきれないことがあります。その結果、キャッシュ不足や借入過多といった問題が発生し、成長戦略そのものが頓挫するケースもあります。
✔ 外部CFOを正しく活用するポイントはこちら
→外部CFOの活用方法はこちら
CFOを採用すべき3つのサイン
社長が「数字を読む」時間を削れない
事業が拡大するにつれ、社長の業務はますます多忙になります。売上や資金の動きを把握し、日々の意思決定に活かすには「財務データを整理して分析する時間」が不可欠ですが、それを社長が担い続けるのは現実的ではありません。
もし「数字を見る時間がない」「読み解くのが不安」と感じているなら、CFOの力を借りるべきタイミングです。数字を“整理し、示す”パートナーがいることで、経営判断の質とスピードが格段に上がります。
借入・補助金・資金管理が属人化している
資金繰りや銀行対応、補助金の申請などを経営者自身や一部のスタッフだけが担当している場合、「属人化リスク」が高くなります。
担当者の退職や急な不在によって、経営資源のコントロールが一気に揺らぐことも少なくありません。
CFOを置くことで、これらの業務を組み”として会社に残すことができ、誰がいても回る体制を作ることができます。
利益は出ているが資金繰りに不安がある
「決算では黒字なのに、なぜかお金が足りない」
– この悩みを持つ経営者は少なくありません。これは、利益とキャッシュフローの違いを理解し、日々の資金の流れを可視化できていないことが原因です。
CFOは、資金繰り表やキャッシュフロー計算書を用いて、「お金が減る理由」「残すための改善策」を明確にします。
利益だけでは判断できない“資金の現実”を見える化し、安心して経営を進められる状態をつくるのが、CFOの大きな役割です。
社内CFO vs 外部CFO|中小企業にとって最適な形とは?
フルタイム採用と業務委託の違い
CFOの導入といっても、必ずしも正社員でフルタイム採用する必要はありません。
中小企業の場合、まずは業務委託型の「外部CFO」からスタートするのが現実的です。
- 社内CFO: 常勤でチームを統括し、内部体制を構築。報酬や雇用リスクは高め。
- 外部CFO: 週数回・月数回のスポットで参画。必要な支援だけを依頼でき、コストを抑えて導入可能。
特に「まずは数字の整理や改善ポイントを知りたい」「フルタイム採用はまだ難しい」という企業にとって、外部CFOは最適な選択肢です。
【詳しくはこちら】
まずはCFO視点での財務診断から
「数字が読める右腕がほしい」
「資金繰りを改善したい」
– そんな思いを抱えたまま、経営判断を先延ばしにしていませんか?財務の見える化は、利益改善・成長戦略・資金調達の土台になります。
まずはCFOの視点で、御社の財務状況を一緒に整理してみませんか?
【無料ご相談はこちら】