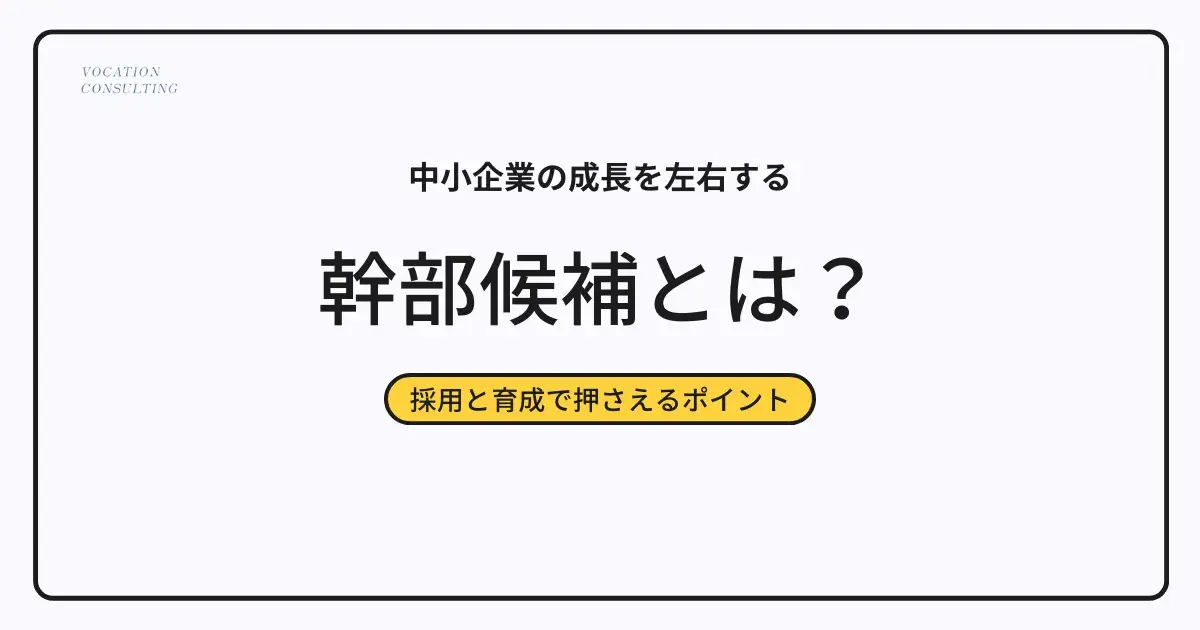「任せられる人が社内にいない」
「次のリーダーが育っていない」
中小企業の経営者や人事担当者から、こうした声を聞く機会が年々増えています。事業が安定・成長フェーズに入るほど、「幹部不在」は深刻な経営課題となりやすく、社長や一部役員に負荷が集中し、組織の拡張スピードにブレーキがかかる場面も少なくありません。
では、幹部候補は「社内で育てるべき」なのか、それとも「外部から採用すべき」なのか。どちらか一方が正解というわけではなく、中小企業においては経営の未来を見据えた“戦略的な仕込み”が重要です。
本記事では、
- 幹部候補の定義とよくある誤解
- 採用と育成、それぞれの実践メリットと注意点
- 幹部不在を回避するための中小企業向け設計ポイント
を、具体的に解説していきます。経営の“次の一手”を担える人材を、どう準備するか。その答えは、今日の視点と行動から始まります。
そもそも「幹部候補」とは?企業にとっての本当の意味
「幹部候補」という言葉を耳にしたとき、どのような人物像を思い浮かべるでしょうか。多くの場合、「現場で成果を上げている人」「業務が早くて頼れる人」が挙げられます。しかしそれは、“優秀なプレイヤー”であっても、幹部候補とは限らないということを意味します。
幹部候補の本質は、“経営視点”と“未来志向”にある
幹部候補とは、単に現場をこなす人ではありません。自らの役割を超えて、組織全体や事業の未来を見据えた判断ができる人材こそが、真に幹部候補と呼べる存在です。
たとえば:
- 目の前のKPIだけでなく、組織や顧客の構造変化に目を向けている
- 自部門だけでなく、他部署・経営全体の連動性を意識している
- 長期視点で「どうすればこの会社は強くなるか」を自ら考え行動する
こうした視座を持つ人材は、組織の中で時間をかけて育てることもできますし、外部から“経営を動かせる人材”として迎え入れることも可能です。
「優秀なプレイヤー」=「幹部候補」ではない理由
中小企業においては、現場で活躍する人をそのまま幹部に据えるケースがよくあります。しかし、プレイヤーとしての優秀さと、マネジメントや経営判断の適性は、まったく別の資質です。
- 高い成果を出していた社員が、管理職になった途端に悩み始めた
- 意思決定を求められたとき、組織全体の視点がなく判断が遅れる
- 現場と経営の板挟みになり、本人もチームも疲弊してしまう
こうした事例は、「そもそも“幹部の定義”が明確でなかった」ことに起因することが少なくありません。
幹部候補の存在が、中小企業を“属人経営”から救う
中小企業では、社長や創業メンバーがすべてを判断・実行しているケースが多く見られます。しかし、事業が拡大すればするほど、それはスピードと再現性の壁にぶつかります。
幹部候補を社内に設け、育て、任せることは、
- 経営判断の分散
- 組織的意思決定の仕組み化
- 次世代経営の準備
につながります。これは単なる「ポジション補充」ではなく、組織そのものを“未来に強くする仕組み”の第一歩なのです。
中小企業が抱える「幹部不在」の構造的課題
幹部人材の重要性は理解していても、現実には「幹部が育たない」「採用しても定着しない」といった課題に悩まされる中小企業は少なくありません。その背景には、単なる人材不足にとどまらない“構造的な課題”が存在します。
育たないのではなく、「育つ環境」が整っていない
多くの中小企業では、「幹部を育てたい」という思いはあるものの、実際には以下の3つの設計不足が見受けられます:
- 任せていない:責任の一部を委ねる文化がなく、結局すべてをトップが抱えている
- 育成設計がない:どのように幹部として成長すべきかの基準やプロセスが存在しない
- 期待を伝えていない:本人に「将来の幹部候補」としての意図が共有されておらず、気づいていない
これでは、たとえポテンシャルのある人材がいても、自発的に幹部として育つことは難しく、属人的な経営体制から抜け出せない状況が続いてしまいます。
社内には眠れる幹部候補がいるかもしれない
実は「幹部不在」に見える組織でも、既存社員の中に幹部候補となり得る人材がいるケースは少なくありません。しかし、それを見極め、意図的に育成する仕組みがなければ、プレイヤーとしての仕事に埋もれ、本人の意欲も伸び悩んでしまいます。
「育てる」視点を持たずに日々を回しているだけでは、いざポジションが空いても適任者がいないという状況に陥ります。
外部採用も簡単ではない。幹部層の採用市場の現実
「だったら外から採ればいい」と思っても、幹部候補となる人材は市場にそう多く存在するわけではありません。
特に中小企業の採用においては、以下のようなハードルがあります:
- そもそも転職市場に出てこないハイレイヤー人材が多い
- 求人票だけでは「どのような役割か」が伝わりにくい
- 経営層との相性や組織カルチャーとのフィットが見えづらい
つまり、外部採用にも「戦略的な設計」と「適切なマッチング」が不可欠だということです。幹部不在は、偶然ではなく構造の問題です。
以下に、「第3章:幹部候補の『育成』と『採用』どちらが最適か?」という見出しにふさわしい本文を作成しました。
すでに作成済みの内容との重複を避けつつ、読み手である中小企業の経営層・人事担当者が「自社はどうすべきか」と考えやすい構成になっています。
幹部候補の「育成」と「採用」どちらが最適か?
幹部候補を確保するうえで、多くの企業が直面するのが「育てるべきか」「採るべきか」という選択です。どちらにもメリット・リスクがあり、明確な正解があるわけではありません。むしろ、企業のフェーズや組織構造によって、どちらを軸にすべきかは変わってきます。
社内育成のメリット:カルチャーと未来を継承できる
幹部候補を内部から育てる最大の価値は、企業文化を自然と理解している点にあります。長く在籍する中で築いてきた信頼関係や社内事情への理解は、外部人材にはない強みです。
- 自社の価値観・判断基準に基づく意思決定ができる
- 組織の変化に対して、過去と未来をつなぐ文脈を持てる
- 中長期視点で“自社らしい幹部像”に育てていける
特に、理念重視の経営を行う企業や、事業継承を視野に入れるケースでは、社内育成が非常に有効です。
外部採用のメリット:経営のスピードと構造を変えられる
一方、外部から幹部候補を迎えることで得られるのは“変革力”と“即戦力”です。
- 戦略立案や実行において即座に貢献できる
- 組織にない発想やフレームワークを持ち込み、刺激を与える
- 「社内のしがらみ」から自由な立場で、客観的に課題を捉えられる
特に、第二創業・事業転換・IPO準備といったタイミングでは、外部人材のほうがドライバーになりやすい場合も多く、社内にないノウハウを“借りる”意味でも有効です。
結論:育成か採用か、ではなく「両輪」で仕組む視点を
幹部候補の確保は、どちらか一方に偏ると限界が来ます。
- 育成だけでは、成長スピードに追いつかない
- 採用だけでは、組織の文化や関係性にフィットしづらい
そのため、重要なのは「育成×採用」のハイブリッド戦略です。
社内では育てる仕組みを構築しつつ、外部からは新しい視点と専門性を注入する。この2つを同時に機能させることで、幹部人材に“多様性”と“持続性”を持たせることができます。
幹部候補の採用に失敗しないためのチェックポイント
外部から幹部候補を採用することは、企業の変革を加速させる有効な手段です。しかし、経営に直結する重要ポジションである以上、「何となく良さそうだから」で採用してしまうと、ミスマッチや早期離職を招きかねません。
幹部層の採用を成功に導くには、「人材のスペック」だけでなく、採用の設計段階から戦略的に考えることが重要です。ここでは、採用時に必ず押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
1|求める人物像は「理想」ではなく「役割」から逆算する
幹部候補の採用で最も多い失敗は、「こういう人が来てくれたらいいな」という曖昧な理想像に引っ張られてしまうことです。まず定義すべきは、「このポジションに何を任せたいのか」「どんな経営課題を解決してほしいのか」。
そこから必要なスキル・経験・人物特性を具体的に落とし込みましょう。
- 今抱えている課題(例:事業開発、採用強化、マネジメント再構築)
- 任せたい範囲(戦略立案までか、実行管理も含むか)
- 関与スタイル(フルタイム、業務委託、プロジェクト単位 など)
役割から逆算することで、選考基準も明確になり、ミスマッチを防げます。
2|経営陣・現場との“カルチャーフィット”を見極める
幹部人材の離脱理由で多いのが、「成果を出しても評価されない」「現場からの協力が得られない」といった相互理解の不一致です。スキルや実績だけでなく、次のようなカルチャー的な相性もチェックしておくことが不可欠です。
- 組織の価値観や意思決定のスピードに適応できるか
- 社長との距離感(右腕的な動き方ができるか)
- 現場を巻き込むコミュニケーションスタイルがあるか
特に中小企業では「人間関係がすべて」と言っても過言ではありません。組織の“温度”にフィットするかどうかを、面談や現場同行などで丁寧に見極めることが重要です。
3|CxO・幹部層に強い専門エージェントの活用を検討する
幹部クラスの人材は、一般的な採用手法では出会いにくいポジションです。転職市場に出回らない「潜在層」も多く、自社採用だけでは候補者数・質ともに限界があるのが実情です。
そこで効果を発揮するのが、CxO採用やハイレイヤー人材に特化したエージェントの活用です。
- 自社の経営課題をふまえたポジション設計のアドバイス
- 市場に出ていない候補者層へのアプローチ
- 面談時の評価ポイントや交渉支援のサポート
これにより、表面的なマッチングではなく、“経営のパートナー”としての適合性を軸にした採用が可能になります。
幹部採用は、単なる人材補充ではありません。経営そのものを託す存在を、どう迎え入れ、どう機能させるか。この視点があるかどうかで、成果にも大きな差が生まれます。
社内で幹部候補を育てるためのステップ
「幹部候補を育てたい」と思っていても、実際に育つ仕組みがなければ人は伸びません。中小企業の中には、「経験を積めば自然と育つだろう」と場当たり的なアプローチにとどまり、結果的に次世代リーダーを失ってしまうケースも少なくありません。
ここでは、育成を“偶然”ではなく“仕組み”に変えるための3つのステップをご紹介します。
1|成長基準とキャリアパスを明文化する
「幹部候補として育てる」と言っても、何をもって成長とするのかが曖昧では、本人も育成側も手応えを得られません。まず必要なのは、「どこを目指し、何ができれば幹部としての準備が整ったと判断するのか」というキャリアパスと評価基準の明確化です。
たとえば:
- 経営会議での発言力・意思決定への関与
- チームマネジメントと目標達成への再現性
- 自発的に事業課題を捉え、提案・改善できる能力
このように、段階的な成長指標を定義し、評価・フィードバックと連動させることで、「何をすれば上を目指せるのか」が可視化され、意欲も継続しやすくなります。
2|経営に“触れる機会”を意図的に設計する
実務でいくら成果を出しても、経営の視座は「体感」なしには育ちません。幹部候補としての成長を促すには、経営判断や戦略策定に間接的でも関わる機会を早期に設計することが不可欠です。
具体的には:
- 経営会議への同席や、戦略合宿への参加
- 新規事業や社内改革プロジェクトのリーダー任命
- 月次報告だけでなく、数字をもとにした分析・提言の場を与える
これにより、“経営の言語”に慣れ、意思決定の重みやプロセスを肌で理解する経験が蓄積されていきます。
3|フィードバックと評価制度を“育成前提”に見直す
幹部候補の育成を組織全体で支援するには、日々のフィードバックと人事評価制度も連動している必要があります。
- フィードバックでは「できた/できない」だけでなく、「どの視点が経営者的だったか」を伝える
- 評価制度では「プレイヤーとしての成果」だけでなく、「組織貢献」「経営視点での行動」を項目化する
- 半年〜1年単位で育成プランを明文化し、定期的に対話する機会を設ける
これにより、「評価=幹部候補としての成長指針」という仕組みが組織内で機能しはじめます。
幹部候補の育成は、属人的な引き上げではなく“構造設計”として捉えることがポイントです。
まとめ:幹部候補は「採る」「育てる」ではなく「戦略的に仕込む」もの
「幹部候補が育たない」「任せられる人がいない」──
こうした声が増える背景には、育成も採用も“戦略の不在”によって偶発的に進められているという共通点があります。幹部候補は、放っておいて育つものではありません。
現場での成果だけで自然と幹部になる時代は終わり、明確な成長基準と役割設計、経営との接点、評価制度との連動といった“仕組み化”が欠かせません。特に社員数500名以下の中小企業においては、組織のフェーズ転換や経営課題の変化に対し、幹部層の質がそのまま事業のブレーキ/アクセルを左右する要素になります。
だからこそ、今このタイミングで、「仕組みとして幹部候補を仕込む」判断が重要です。
また、すべてを自社だけで完結する必要はありません。必要であれば、外部の知見やプロ人材を活用することも立派な経営判断のひとつです。
たとえば、CxO(経営幹部)ポジションを社外から迎え入れることで、変革と仕組み化を一気に加速させる選択肢もあります。
▶ CxOとは?導入メリットと役割
「CxO候補を社外から検討したい」
そんな企業様は、ぜひ一度ご相談ください。事業ステージに応じた最適な人材戦略を、私たちが伴走型でサポートいたします。
▶ 今すぐ問い合わせる